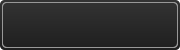50「楽譜を見ないで演奏するって大変だけど」
2025/02/19
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。
楽器を演奏するとき
コンサートや
発表会などでは「暗譜」が基本です。
暗譜=楽譜を見ない
演奏家にとって楽譜を見ないで楽器を演奏することは
必須条件です。
オーケストラをバックにソリストとして弾く場合や
ヴァイオリンだけで一人で演奏するときなど
暗譜が必要です。
ただし
絶対ではありません。
現代曲など、直前まで作曲家と協議しながらの初演や
室内楽での演奏
まぁ、
なんなら、
いつも楽譜を見て弾いてもいいんですよ・・・
でも、
私の場合は
「やっぱりこの曲は暗譜よね・・」っていう曲もあるので
暗譜の訓練はします。
(ヴァイオリン独奏で弾く時は
なるべく楽譜を見たくないです。
その方がカッコイイから!)
生徒さんには
これも訓練なので
よほどのことがない限り
暗譜の練習もしてもらいます。
特に子どもの生徒さんは
しっかり訓練します。
その練習が他のことにも役立つからです。
大人の生徒さんには強要はしませんが
難しい場所などは
「この部分だけ暗譜しちゃいましょう!」と
お伝えします。
その方が、すんなりと弾けることも多いからです。
(視覚が楽譜をみるという作業を放置することによって
左手と右手を目視して集中して弾くことができる)
暗譜にはさまざまな方法があるのですが
私は
「頭の中の楽譜をめくっていくように」
暗譜していきます。
曲の構成(ブロック)を頭に入れて
その区切りが楽譜のどのあたりに書かれているのか
確認します。
(たとえばABAなのかABCAなのかAA'BB'CC'なのか・・・など)
同じような繰り返しだけど
ちょっと変更部分があるところを
念入りにチェックして
その場所が何ページ目の何段目なのか確認します。
覚えにくいなぁ、と思うところ
(もしくは速いテンポで音のたくさんある場所)
から暗譜を始めて
何回も出てくるフレーズは
その場所が他にどこに書いてあるのか
番号をつけてチェックします。
ここまで来たら
あとは頭の中の楽譜を頼りに
練習するのみ。
アナログ方式かもしれませんが
自分の脳は、自分のやり方で
操縦するしかないのです。
そのうち
指や身体に曲が染みついて
無意識に指が動くようになってきます。
(その無意識が怖いから注意が必要なんですが)
最初から音をひとつずつ覚えていくのではなく
かたまり(ブロック)で覚えていくことが大切です。
この方法は自分で考えて習得しました。
生徒さんは曲が仕上がってきてから
暗譜の練習になるまで
少し時間がかかります。
どのくらい頭の中に楽譜をきちんと保存しているか?
私からのチェックが厳しいからです。
曲の構成は?
和音の変わるところは?
音の大きさが変化するところは?
音が変わる場所は?
???
中途半端で暗譜を開始すると
余計な時間がかかることもあります。
(私がアレコレ諮問をすることは
意地悪をしているわけじゃないんですからね)
説得力のある演奏をしてもらいたいから
細かいところにこだわります。
暗譜ができるようになると
自由になってきます。
自分が表現したいことを
色々と試してみることが楽しくなります。
音楽が色彩豊かに
より演奏者に近づいていく感じになっていきます。
そうなれば
もうこちらのもの。
本番を楽しむ、という域に達してきます。
ただ
最近の私は
記憶力の低下ととに
楽譜を見て演奏したい欲が高まります・・・
やはり、安心ですから。
暗譜に失敗して
どこを弾いているのかわからなくなり
頭が真っ白になって
演奏が止まってしまったらどうしよう・・・💦
(そんな経験は今までにありませんが・・・)
それでも、敢えて暗譜の道を選んで
四苦八苦して自分を苦しめることもあります。
本番前は心臓が口から出てきそうなほど
緊張しますが・・・
人生、チャレンジ。
ううむ。
しかし
いつまで暗譜で弾けるかしら~・・・
関連エントリー
-
 44「りうまーミートアップ@東京に参加しました」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。りうまーミートアップ@東京に参加しました。昨日
44「りうまーミートアップ@東京に参加しました」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。りうまーミートアップ@東京に参加しました。昨日
-
 45「ホームページを改良していきます」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。私のホームページはずっと放置状態でした。自分の
45「ホームページを改良していきます」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。私のホームページはずっと放置状態でした。自分の
-
 46「二十四節気とともに季節を歩いていく」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。少しずつ春の息吹を感じる毎日です。木々の新芽が
46「二十四節気とともに季節を歩いていく」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。少しずつ春の息吹を感じる毎日です。木々の新芽が
-
 47「積読・2月の進捗」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。積読その後の状況・・・着実に消化しています。(
47「積読・2月の進捗」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。積読その後の状況・・・着実に消化しています。(
-
 48「無伴奏曲を弾くとき」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。今年のリサイタルの曲目を絶賛思案中。頭の中がい
48「無伴奏曲を弾くとき」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。今年のリサイタルの曲目を絶賛思案中。頭の中がい