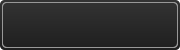- ホーム
- ブログ
ブログ

59「毎日を見直す」
2025/02/28
58「小さいことの積み重ね」
2025/02/2757「好きを見つけるのは、なかなか難しい」
2025/02/26
56「自分の好きを見つけていく」
2025/02/25
55「ピアノのメンテナンス」
2025/02/24
54「選ばれる人に」
2025/02/23
53「土曜日の思い出」
2025/02/22
52「閑話休題・報告文を書いてみる」
2025/02/21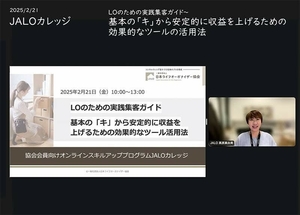
講座は「集客の前に自分がライフオーガナイザーとしての土台がしっかりしているか」という問いからスタートしました。
自身を振り返る中で「収入面の数字化」ができていない点を反省し、より細かな生活の記録を取る必要性を感じました。
次に扱われたのは、ブランディングとポジショニングについてです。
「自分はどんなイメージで進むのか」「市場の中でどのような立ち位置を目指すのか」を考える重要性が強調されました。
加えて、どのようなツールを使って情報を発信していくかについての具体的な方法も学びました。
私自身は「思考」についての講座やサポートを目指したいと思っているのですが「伝わりにくい」部分が多いという欠点をより意識する必要があると感じました。
また、今回特に知りたかったライフオーガナイザーの仕事をする上での「導線」に関する内容についてもしっかりとメモを取りました。
講義中に高原さんがおっしゃった
「自分が満足するものなんて永遠に出来上がらない。まずは出してみて、さまざまなフィードバックをもらいながら修正していくもの。出したものがないとブラッシュアップはできない」という言葉が心に残り、まさにその通りだと改めて実感しました。
この1年間さまざまな時期と場所で、こういった課題を学んでいますが、アタマの回転がなかなかうまく働かないので、何度でも聞いて咀嚼をしたいと思っています。
今回はさらに、講座を受講する際のメモノートの取り方を工夫してみました。
ノート1ページの3分の1を自分へのメモ部分として、質問したいこと、その時閃いたアイデアなどを書いてみました。
今更ながら、講座受講の姿勢も大切なことだなぁと思いました。
- 報告分を書く
- ChatGPTを使ってみる
51「暗譜は目を開く?目を閉じる?」
2025/02/20
- とにかく弾きまくって覚える→ちょっと時間がかかりますが、確実な方法です。体育会系のイメージですね。
- その曲のイメージを絵にかいて覚える→小さいお子さん向けですが、自分のイメージがしっかりしているとすんなり覚えることができます。
- 歌って覚える→これも短い曲を暗譜するお子さん向けですが、大人の生徒さんにもとても有効です。私も時々鼻歌を歌いながらフレーズを覚えているときがあります。
- 弓を使わないで左手だけ動かして弾く練習→左手の動きに集中することによって、目視で音を記憶しているということにつながる。
50「楽譜を見ないで演奏するって大変だけど」
2025/02/19
49「楽譜を目で追う練習」
2025/02/18
48「ヴァイオリンを弾くことは哲学?」
2025/02/17
- 目で楽譜を認知し
- 脳が素早く
- 的確な位置に指を動かす指示を出し
- 耳が瞬時に音程をキャッチして
- 微調整し
- 記憶にある自分の音を探し出して
- 音楽を創っていく
47「100本のチャレンジをすること」
2025/02/16
- 一緒に頑張っている人がいるから
- HP運営会社の社長が毎日コメントをくれるから
46「春の始動へ向けて整えています」
2025/02/15
45「音楽家と言葉」
2025/02/14
44「習い事に思うこと:娘たちの場合」
2025/02/13
43「ヴァイオリンを習うことはサードプレイスを得ることでもある」
2025/02/12
42「ビールもヴァイオリンも練習」
2025/02/11
41「いろいろなコンサート」
2025/02/10
40「音楽家は美味しいものが好き?」
2025/02/09
39「脳を休ませることの大切さ」
2025/02/08
38「姉妹:私の場合」
2025/02/07
私には姉がいます。
5歳半(6学年)違うので
幼い頃はまるっきり相手にしてもらえませんでした。
喧嘩なんて、一方的に私が挑んでいるだけで
姉はずっと知らん顔してました。
勉強家で真面目。
時々ポロリと面白いことを言うけれど
周りの人が気がつかないこともあったりして
近くにいる人だけが笑っている。
運動神経もそこそこあって
直線を走るのはものすごく速いのに
障害物競走になると途端に
あれ?どこ行きました???・・・
両親も姉への信頼は絶大で
期待も大きかったです。
「お姉ちゃんなんだから」
「しっかり勉強しなさい」
今の時代ではNG表現のことを
当然のように言われていたな、と。
私の分まで怒られていることもありました・・・
(次女あるあるの要領の良さで)
姉は語学の才能があり
ドイツ語・英語は問題なく話せて
フランス語も「なんとなくわかる」らしいです。
独立心の強い姉は、17歳の時にドイツの音楽大学に入り
独り暮らしをしながら
生徒を教える音楽教室の先生にもなり
学士過程、修士課程を終えて
コンサートピアニストという称号を得ました。
もちろん、途中で体調を崩したり、
家族にとっては意味不明なこともしていました。
だから、私たち姉妹が一緒に暮らした時間は
11年に満たないくらいのもの。
「ひとりっこ」が2人いるような感じでした。
彼女の得意とするのはピアノ教育。
演奏家として舞台に出るというより教育者として
生徒さんを指導することに喜びを感じていました。
日本に帰国してからも、指導者としての仕事中心でしたが
50代半ばで病気から失明し、盲目となりピアノを辞めました。
自宅からピアノを運び出す日
私も一緒にピアノを見送りました。
彼女の音楽家人生の終わりでした。
それからのち
白杖歩行訓練や点字練習、安全に生活をするための
新しい生活様式を学び
長く長く、苦しい時間を経て、
彼女は今、点字教室の指導をしています。
「やっぱり教えることが好きなの。
生徒さんにいろんな可能性を伝えることに燃えるのよ!
アレコレおせっかいなのよ、私」と話す姉はいつも生き生きしています。
↓姉のポッドキャスト
私自身の子どものころは
ヴァイオリンを弾くより
身体を動かしているほうが得意で
お勉強はまぁまぁ・・・
体育の成績だけはずば抜けて良くて
音楽高校を受験するときは
最後の最後まで悩みました。
体育大学に行った方がいいかも、って。
ヴァイオリンの練習だって
当時、2時間程度が限度のお粗末さ。
両親もため息をつきながら
「あなたは本当に体育が好きよね」と
半ば呆れるように
目の奥は「仕方ないわね~」といった諦めが
透かして見えるような物言いでした。
それでも
体育の道を選択することはなく
ヴァイオリンを相棒にすることに決めて
弾き続けることにしたのです。
多分「これが私の道かな」と直感がささやいたから。
音楽の道に進んでからは
同学年の友人に刺激を受けて
勉強し
練習を重ねて
七転八倒しながら
頭をひねり
まだまだ
今もなお弾き続けています。
「やっぱりヴァイオリンを弾いているときが自分らしいかな」と思うから。
でも、いつ何かが起こってヴァイオリンが弾けなくなるかもしれません。
私は姉のように多才ではないので、そんなことになったら不安しかないですが・・・
そんなことになったらどうしよう・・・
(考えをやめよう)
姉との6学年差の大きさは
時に意地の張り合いになり
競争相手になり
価値観の違いをぶつけ合い
お互いに傷つくことが多かったものが
今では「同じ年代」となって
穏やかな関係になりました。
姉が私の存在を
「小さな何もできない妹」から
少しだけ認めてくれたからかもしれません。
個性が違い
目指すゴールが違い
生活スタイルも全く違う
私たち姉妹。
それでも何か
そこはかとなく
共通点があります。
それは根底に流れる家族の基盤なのか
同じ音楽家という道を経験しているからなのか・・・
月に1回程度
定期的に会う姉妹の会。
相変わらず私は「妹」という立場に甘えて
ヘラヘラしているけれど
それでも姉の盲目になった目の代わりに
外側から彼女の心の奥を覗いているつもりです。
37「オクターブ練習に思うこと」
2025/02/06
36「もくもくと(孤独に)練習する音楽家のひとりごと」
2025/02/05
35「五感を大切にする生活を」
2025/02/04

34「ヴァイオリニストのアクセサリー事情」
2025/02/03
- ネックレスはしない
- 垂れ下がるピアスはしない
- 指輪は右手だけ
- ブレスレッドはしない
- ビーズ飾りのものは極力避ける
33「娘たちとの会話」
2025/02/02
32「本物をみる」
2025/02/01
-
 23「リサイタルの準備はじめています」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。今年のリサイタルのプログラムを思案中です。この
23「リサイタルの準備はじめています」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。今年のリサイタルのプログラムを思案中です。この
-
 24「一日を彩る音たちとともに」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。寒い毎日。外出を極力控えて家にこもっています。
24「一日を彩る音たちとともに」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。寒い毎日。外出を極力控えて家にこもっています。
-
 25「春の兆しを感じる1日」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。年下のお友だちとの女子会。クリエイティブなお仕
25「春の兆しを感じる1日」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。年下のお友だちとの女子会。クリエイティブなお仕
-
 26「冬の光を実験する」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。試験的に色々な写真を撮っています。被写体は色々
26「冬の光を実験する」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。試験的に色々な写真を撮っています。被写体は色々
-
 27「お花のサブスクが運ぶ思い出」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。先日、毎月届くお花の定期便にフリージアが入って
27「お花のサブスクが運ぶ思い出」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。先日、毎月届くお花の定期便にフリージアが入って