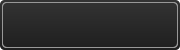- ホーム
- ブログ
ブログ

31「ヴァイオリンの乾燥対策」
2025/01/31
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。
https://item.rakuten.co.jp/miyaji-onlineshop/sr19-7203/
https://item.rakuten.co.jp/mikidj/898775001052/
お天気の良い日が続いています。
太陽の陽ざしがまぶしい。
朝起きてお天気が良いと
それだけで得した気分になりますね。
しかし・・・乾燥が激しいです。
手荒れ・顔がパリパリ・きっと体の中もカサカサで
水分が足りていないのを感じます。
自分自身のケアは、自分で何とかできますが
さて、ヴァイオリンはどうなんでしょうか?
もちろん乾燥しています。
基本的にヴァイオリン自身は西洋の楽器なので
乾燥したヨーロッパの風土に合わせて作製されています。
乾燥に関してはそれほど神経質に考えなくても良いと思いますが
近頃の日本の気候変化には
ちょっと注意が必要かもしれません。
近年の日本は暑くて長い長い夏。
湿気を含んだ空気、とにかく気温の高い毎日。
楽器も人間もヨロヨロになります。
それから
急激に冬に移行してあっという間に厳冬時期。
この頃は秋という季節がほとんどありません。
降水量も急激に減ってしまう関東地方の気候は
ヴァイオリンにとって過酷な状況です。
私の場合は12月のリサイタルを終えた後は
楽器も私も休養時期のため
細かい状態の把握ができていない場合もあります。
なんだか音がバラバラになっている
カサカサした音がする
???
なんだかおかしい・・・(感覚だけ…)
そんな時はたいてい乾燥していることが多いです。
私の楽器には湿度計がついているので
チェックしながら
適宜加湿器を楽器内に入れています。
以前の私はこんなものを活用していました↓
楽器のエフ字孔から差し込むという
単純な道具です。
- 3時間くらい水につけておく
- 内部のスポンジを十分に水で湿らせる(コップに水をためてその中に浸しておく)
- 外側の水滴をきちんとふき取ってエフ字孔から差し込む
演奏するときには外しますが
そのほかの時に楽器を内部から加湿をしてあげることができます。
しかし
- 楽器に直接触れるのが気になる
- エフ字孔が小さすぎて入らない
などの不具合があります。
長女が使っているものがコレ↓
ジェル状になっているので液だれすることなく
楽器内ではなく楽器ケースの内部にくっつけるタイプなので
安心感はあるかもしれません。
私自身は
もともと楽器に装着してあった加湿ケースを
そのまま利用しています。
楽器自身の耐久力も大きく左右されるかもしれません。
制作されて年数の浅いものは
まだまだ季節の経験が少なくて不安定ですが
オールド楽器は長年の知恵から
楽器自身が順応しているような気がします。
楽器を弾く自分たちが
ヴァイオリンと対話して調整することが大切です。
30「音楽の道・娘たちの場合」
2025/01/30
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。
我が家には二人の娘がいます。
どちらも音楽の道を修行中です。
さて、生徒さんに対しては辛抱強い私ですが
やはり自分の子どもになると
そうもいかないことは
早い段階でわかっていました。
そのため、娘たちの手ほどきの先生は私ではありません!
長女は半ば私の勉強のためにつき合わせたようなもの。
(初心者さんの指導に詳しいベテランの先生だったので
レッスン方法などを学びたかった)
次女は長女のレッスンに毎度付き合っていたのでその流れで一緒に。
・・・
大きな志があって始めたわけではないので
いつ辞めてもいいよ、というスタンスでした。
音楽家は一家に一人で充分、と思っていましたから。
ただ、レッスンとレッスンの間は私がチェックしなければなりません。
その時は辛かった・・・
音程の悪さにキレること数え切れず
練習を促すのに必死の形相になる(自分の母の姿を思い浮かべながら)
レッスンへの心構えをひたすら教え込む
考えをじっと待つのも、生徒さんと比べて5分の1くらい
早くしなさ~い、と叫ぶのは毎度のこと
・・・
そのほかにも自分の問題も山積。
レッスン料の新札交換に銀行へ走る
自宅練習時間の配分と練習時間に付き合う自分の時間の確保
(自分の練習もしなくちゃならないけれど、日中は確保できないので
ほぼ夜中にキッチンで練習・体力温存)
レッスン時間に間に合うように二人のスケジュール管理
・・・
習い事をするのは本当に大変です。
自分で練習することができるようになるのは小学校高学年くらい。
それまでに整えておけば
その後は少し遠くから見ることができます。
私はわかっているけれど
本人たちが自分で理解できるようになるのは
また別の話。
「お母さんがヴァイオリニストで良いね」
なんていう言葉は、はっきり言って
「放っておいて~」です。
あちこち寄り道しながら
試行錯誤して
ふりだしに戻ったり
モチベーションが空っぽになったり・・・
全然余裕がありませんでした。
・・・
私は娘たちに、
あの頃どんな思いでヴァイオリンを弾いていたのか
怖くて聞くことができません。
でも、未だに弾いているということは
無駄なことに時間を費やしたわけじゃない・・・と思いたいです。
何か学ぶことがあったから
続けているのだと。
学んだことが、ヴァイオリンを演奏することだけではなくても
音楽を通して経験できたこと
社会生活でも、コミュニケーション術でも
歴史の勉強でも、心理学でも良いと思います。
もし娘たちが音楽以外の道を見つけたとしても
その道を極める素地はちゃんと整っていると
自信をもって見守ることができると思います。
自分の人生は自分で舵を握るべし
29「冬の日の遊び・音」
2025/01/29

こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。
陽の光は暖かく感じても
風の冷たさはやはり身に沁みます。
子どものころ、田んぼの近くに住んでいました。
四季を通じて田んぼの表情の変化を見て育ち
今でも懐かしく思い出します。
今住んでいるところも、ほんの5分ほど歩けば
田んぼがありますが
気がついたら畑に変わっていたところが多いです。
お米作りはやっぱり手間暇かかりすぎるのかしら?
私は冬の田んぼが大好きで
よく友達と遊びに行きました。
お互いに持っているお人形が少なかったため
家で遊ぶより
外で飛び回っているほうが楽しくて
次から次へと
日がな一日遊んでいました。
寒い冬の朝、友達と待ち合わせて田んぼに行くと
霜柱が立っているのでそれを片っ端から踏んでいく。
(今思えばよく怒られなかったなぁ・・・)
ガサガサ
ぽこぽこ
ゴボゴボ
ざくざく
霜柱の大きさによって音が違う。
友だちと追いかけっこしながら田んぼを走り回って
飽きてきたら
田んぼに隣接する野原で
セーターに「ひっつきむし」をくっつけて
自作のブローチにする遊び。
冬の陽だまりはほんのりあたたかくて
大きな枯草のドームを秘密基地に
カサカサと枯草を踏みつけて
探検ごっこ。
夕方になってうす暗くなってきたら解散。
家に帰ると母がストーブの上で
干し芋を炙っている。
ジリジリという音を聞きながら
美味しそうな香りがしてきたら食べごろ。
アツアツの干し芋を食べて
ヴァイオリンの練習へ・・・
私の4歳ころの思い出は遊んでばかり。
それも外遊びばかり。
でも、覚えているのは
枯草のぱりぱりする音
遠くから聞こえてくる飛行機の音
霜柱の音
キーンと寒い空気の音など
どれも「音の記憶」です。
今でも夕方になると
ご近所のいろんなお宅から聞こえてくる
お皿のカチャカチャいう音や
ボッと音を立てる給湯器の音や
カラン・・というお風呂の音に
耳をそばだてる私がいます。
28「本物の生徒を育てる」
2025/01/28
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。
「本物の生徒とは、自ら学び続けていく人」
どこかで目にした言葉なのですが
私がとても好きな言葉です。
先生として教える側になったとき
生徒さんにはいろいろな事情があって
いろいろな問題を抱えて
どんな思いでヴァイオリンに向き合っているのかを
それなりに見てきたつもりです。
私自身の指導方法は
どれだけ早く弾けるようになるか・・・
コンクールで賞をとるには・・・
といったものではないので
その生徒さん自身が
どれだけヴァイオリンを自分に引き寄せていくのかを
お手伝いしている感覚です。
ヴァイオリンという楽器をリスペクトしましょう!
ヴァイオリンで何を伝えたいのか考えましょう!
自分自身を整えてヴァイオリンにむかいましょう!
そういったところから
レッスンを始めていきます。
そのため、他力から始めた生徒さんは
そのうち自分で考えることが多くなり
「どうしてそう思う?」
「その場所はどんな気持ちで弾くの?」
「あなたはどう思う?」
という私の質問に、常に、自分で答えなければならなくなります。
ずっと黙っている子。
オドオドする子。
キョロキョロして親に助けを求める子。
じっと黙って待ちます。
見学している親御さんの方がドギマギしていますが
辛抱して待ちます。
誰も助けてくれない、
話すまで先に進まないと観念するのか
しばらくすると、なけなしの考えから
ポツリ・・・と言葉が返ってきます。
ひとことで良いのです。
その言葉から、彼らの思いが伝わるからです。
その方法に慣れてくると
彼らは少しずつ自分の気持ちを
言葉にして伝えてくるようになります。
自分で考えるようになるのです。
私の役割は
彼らの思っていることを汲み取りながら
新しい分野・視点を提供することです。
彼らの伝えてくれた言葉を内包しながら
枝葉を広げて
音楽が立体的に
裏付けのある
説得力のあるものに変化する。
それが、音楽を演奏する(再現する)ということだと思っています。
私の生徒さんは
基礎をしっかり学んでいるので
途中でやめてしまってたとしても
やっぱりもう一度、と
再開するときに
それほど苦労はしないでしょう。
弾いていなかったときにも
常に学び続けていたはずですから。
27「ヴァイオリンを習うきっかけはいつでもどこでも」
2025/01/27
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。
私がヴァイオリンを始めたきっかけは
簡単すぎるはじめてのブログでご紹介しました。↓
https://ototabi-kaori.com/contents_76.html
ヴァイオリンをはじめるきっかけは様々です。
特にお子さんの場合はこんな場合が多いかもしれません。
- やってみたいと思ったから
- 親に勧められたから
- 気がついたらお教室に通っていた
どんな理由であれ、私はヴァイオリンに興味を持ってくれたことに素直に感動します。
そして、できるだけ長くヴァイオリンと共に生活してもらいたいと願います。
弾けるようになるだけが目的ではなく
その人の人生に必要なパーツになること
ヴァイオリンによって世界が広がること
その人の喜怒哀楽に寄り添う存在であることが大切だと思っています。
「ヴァイオリンは子どもの時から習わないとダメ?」
そんなことはありません。
私は大人の方に、ぜひヴァイオリンを習ってもらいたいと思います。
まず、両手が全く違う運動方法なので頭を使います。
音程を合わせるために耳に神経を集中させます。
でも
ヴァイオリンがどのような構造になっているかを理解することができる
弦のどこを押さえると、どういう音が出るのかを理論で学ぶことができる
大人ならではの学び方があるのです。
子どもであれば、毎日反復練習をすれば自然に養われるものも
大人であれば、少し近道をして学ぶことができます。
毎日の仕事から離れて、ヴァイオリンという楽器に触れることにより
新しい世界が拓ける。
ヴァイオリンで人生が豊かになるお手伝いができればと思います。
少しでも気になったらご相談くださいね。
26「日曜日と鐘の音」
2025/01/26
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。
今日は日曜日。
ドイツに住んでいたころは、朝の時間に教会の鐘が鳴りだすと日曜日を感じました。
礼拝の時間を知らせる鐘。
礼拝中に鐘を鳴らすタイミングがある場合にはコーンとひとつだけ。
礼拝が終わると高らかに鳴り響く何重もの鐘の音。
礼拝時間はそれぞれの教会によって少しずつ違うので
日曜日の午前中は町中のどこかで教会の鐘が鳴っています。
(礼拝というのはプロテスタント、ミサというのはカトリックですが、内容に大きな違いはなく
聖書朗読、賛美歌、祈り、牧師または神父のお話といった構成になります)
遅くまで寝ていたいのに、ガランゴロンとあちこちの教会の鳴る鐘に
ちょっと不満を覚えた時もありました。今もそうなのかしら?
近頃はキリスト教徒が減少して、牧師や神父の担い手が減り
献金で成り立っている教会運営がうまくいかずに閉鎖に追い込まれる教会もあるらしいです。
私は小学生の頃に父の仕事の関係でドイツに住んでいました。
その頃、自分の部屋から教会が見えました。
窓から外を見れば遮るものもなく正面に見えます。
教会の尖塔が丸くて、黒っぽいレンガ造りで、飾り気の少ない外観。
夜になると、一室だけにポツンと明かりが灯り
私が寝る時間になっても消灯することはありませんでした。
きっと、牧師が一人で、または何人かで勉強をしていたのでしょうね。
何となく心細くなった時にその明かりを見ると、ほっとした気分になりました。
結局、その教会に足を踏み入れたことはなかったのですが
今でもその教会の様子の記憶は鮮明に残っています。
それと同時にどんな鐘の音だったのかも。
カーン カーン
カラン カラン
カララン カララン
カララン(ゴロン)カララン(ゴロン)・・・
だんだん音が増えていって音が重なりあい
異なるリズムが増えて大音響がひとしきりあった後
さぁーっと音が引いて
コーンと一つ音が響いて静寂になる。
日曜日の朝はその音をずっと聞いていたものです。
音の記憶というのは、私にとって鮮明で
未だに鐘の音には特別な思いがこみ上げます。
そして、音楽家となった今は
音楽の中には常に鐘の音が隠れていて
その音を探し当てると
その曲への理解が深まっていくような気がします。
ドイツで一人暮らしをしていたころも、
近くに教会がありました。
自分の生活リズムを刻んでもらっているようで安心感がありました。
日曜日の午前中はぼんやりと窓を開けて鐘の音を聞いていたものです。
私の娘たちは時々、教会と鐘の音の入った動画を送ってくれます。
自分たちの住む町だったり旅行先の町だったり、様々な場所で。
あぁ、なつかしい。
私がどんなに心を揺さぶられて
懐かしい思いに駆られて
あたたかい気持ちになるのか・・・
彼女たちはよく知っているのです。
日曜日に鐘の音を聞かなくなってから
どのくらいになるでしょうか。
でも、記憶の中にある鐘の音は色あせず
今も耳の中で鳴っています。
25「ヴァイオリニストと肩こり」
2025/01/25
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。
ヴァイオリニストが抱える身体の不調のひとつ。
【肩こり】
私はかなり頑固な肩こりに悩まされています。
コンサートが迫ってきて練習時間が増えてくると
左の肩から肩甲骨、腰のあたりまでズシリと重くなります。
ひどい時は頭痛まで・・・
ヴァイオリンを構える姿勢は
どう考えても不自然な形ですものね。
ヴァイオリンを弾くには両肩が前に引っ張られてしまうため
巻き肩になってしまいます。
その上で、左手を酷使して細かく指を動かす運動と
繊細な運弓の動きをコントロールする右手に神経を尖らせて
肩と顎で楽器を挟みながら
耳元で聞こえる音と客席に届いている音を想像して演奏する。
細かく言えば、もっともっとたくさんの神経を使っています。
その神経を支える身体は
頑丈でありながらも
しなやかで
反射神経に優れていなければなりません。
ずっと弾き続けていると
気がつかないうちに癖が染みついて
身体の可動域をずいぶん狭めていることもあります。
一種の職業病だとあきらめつつも
50歳を過ぎたあたりから
何とか自分で自分を手当てするように努めなければ、と
注意しています。
- 楽器を持たずに準備運動をしてから弾き始める
- 早いパッセージ(動き)の曲を急に弾かない
- 適度に腕(指)を休める
- 練習後にストレッチする
上記はとても基本的なことですが
大切なことだと思います。
そして練習後のストレッチは特に重要。
- ゆっくりと胸を開いて肩甲骨を寄せながら呼吸をする
- そのままゆっくりと両手を挙げてゆっくり左右に体を揺らす
「ゆっくり行う」というのが大事です。
反動をつけてしまうと、痛かったり筋を伸ばして
思わぬケガをしてしまうかもしれません。
ヴァイオリンを弾く前後に時間がかかるようになったのも
50歳を過ぎてからです。
マッサージも有効なのですが、一時的なものだったりするので
日ごろのケアを地道に続ける方が良いかもしれませんね。
(あまりにも辛い時は、私もマッサージに駆け込みますが・・・
辛い時に限って時間が無かったりして、結局行かずじまい・・・)
あまり不調を感じることの少ない私自身ですが
小さな違和感は見逃さないように気をつけています。
私は大人の生徒さんには、特にこの運動をお勧めしています。
ただでさえ、ヴァイオリンを弾くということに緊張しているのに
「楽器を落としちゃいけない~」
「左手がうごかない~」
「弓がまっすぐ弾けない~」と
あれこれ考えているとへとへとになってしまいます。
私が「練習した後に、しっかり身体をケアしてあげてくださいね」というと
ハッとした表情から「そうか、そうか~」と笑顔になる生徒さんもいらっしゃいます。
小さい生徒さんも気をつけてあげないと
痛い、窮屈、違和感、というだけで弾けない!、と決めつけてしまう子もいます。
「痛いところがあるの?」と聞いて
どこが痛いのか?
どうして窮屈なのか?
どんな違和感があるのか?
つたない言葉でもいいから先生に伝えることができる。
先生と一緒に考えることのできる生徒さんであってほしいと思います。
近頃の私は、寒くて縮こまって歩いているので
うつむき加減の前傾姿勢💦という姿を反省して
冷たい北風に立ち向かうように
偉そうに歩くことにしました。
(寒さが一層身に染みる)
24「ピアノ好きのヴァイオリニスト」
2025/01/24
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。
指の動かない冬の季節。
まだまだ寒い日が続きますね。
私の場合、練習を始めるときに
ちょっと気持ちがヴァイオリンに向いていないときは
ピアノを弾いています。
ピアノの蓋をパカっと開いて鍵盤をさわれば音が出ます。
なんて簡単な!ピアノって最高~!
自分の弾けそうな(もしくは好きな曲の)曲集は
すでにピアノの上に置いてあります。
ドビュッシー:子供の領分
ドビュッシー:アラベスク
ドビュッシー:ベルガマスク組曲
ラフマニノフ:鐘(前奏曲作品3-2)
メンデルスゾーン:無言歌集
ベートーヴェン:ソナタ集
ブラームス:ラプソディ
今、練習しているのはショパンのエチュード作品10第1番。
ショパンはなかなか弾けるようにならないのでチャレンジ。
レッスンがあるわけでもなく、もちろん本番があるわけでもないので
仕上げることが目的ではありません。
でも大丈夫。
単純に楽しめばいいのです。
「ゆっくりだったら、なんとか最後まで弾けそう」
「そういえば、姉さんはあんな風に弾いていたなぁ」
「このフレーズは何度も出てくるからスムースに弾ける~」
「昨日より和声が頭に入っている~」
「弾ける、うれしい!」
それだけで充分。
耳が音に慣れてくると、
自然にヴァイオリンの音を創りたくなります。
ピアノの両手で鳴らす音の多さと
ヴァイオリンの一音で鳴らすことのできる音の数は全く違います。
ピアノ曲のある一部分をヴァイオリンに任せるとしたら
どんな音にしようかしら?
どんな風に弾こうかしら?
そんなことを思いながら
徐々にヴァイオリンの練習へとシフトしていきます。
それもこの時期だからできること。
準備時間にじっくり時間をとれるからこそ。
大事な時間です。
コンサートが迫ってきたら
準備運動練習もそこそこに
曲を仕上げることに焦りまくります。
「計画的にやろうよ、自分💦」
本番前に何度つぶやく言葉か・・・
今年は少し、練習方法のアプローチも変化させていこうかと思案中です。
23「ヴァイオリンで人生が豊かになるには」
2025/01/23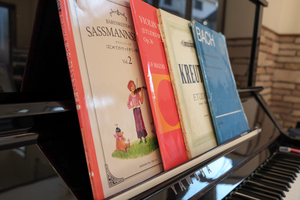
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。
ヴァイオリンの先生として私は厳しい方かもしれません。
弾ける、弾けないという指導よりも
お行儀や態度、道具への丁寧さを求めます。
「ヴァイオリンは自分で持ってレッスンに来ましょう」
「脱いだ靴は自分でそろえましょう」
「楽譜は丁寧に角をそろえて譜面台におきましょう」
「ヴァイオリンは丁寧に扱いましょう」
「先生が話すときはきちんと先生の顔をみましょう」
「先生が話し始めたらすぐに弾くのを止めましょう」
「レッスンのはじめとおわりにきちんと挨拶しましょう」
「レッスン料は生徒が自分で御礼とともに先生に渡しましょう」
「玄関でのさよならのあいさつはしっかりとしましょう」
生徒さんはもちろんのこと、その親御さんにもきちんとした態度を求めます。
え~・・・メンドクサイ・・・
そう思いますか?
でもこれって、普段の生活でも必要なことですよね。
社会生活の基本的なことばかりをレッスンに置き換えているだけです。
一見当たり前に思えるような事でも
流れるような動作になるまでには時間がかかります。
でも、覚えてしまえば様々な場所で応用が利きます。
そして、自信になるのです。
どんな緊張する場所に行っても、同じ手順であれば安心できる。
たとえ国を越えて海外に出ていったとしても通用します。
芸事は型から学ぶ
基本がしっかりとできていれば
その後は自在に自分を変化させることができます。
私の生徒さんは、初めは驚くものの
だんだんと習慣化されて
当たり前のように落ち着いたレッスン受講態度になっていきます。
始めはできなくて当たり前。
でも、レッスンに通うことによって徐々にできるようになっていきます。
子どもはもちろんのこと、大人でも同じことです。
ヴァイオリンを弾くことだけが目的ではないレッスン。
ヴァイオリンとともに豊かな人生を歩むお手伝い。
そんな先生になろうと改めて思っています。
22「コンサートを妄想する」
2025/01/22
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。
寒い時期はひきこもって勉強しよう、と決めて
引き籠りすぎて久しぶりに外へ出かけたら
フラフラしてしまった私です。
さらに、会議でマイクをもって話さなければならず
自分の声のトーンが暗すぎて焦りました💦
何事もほどほどにしないといけない・・と反省です。
音楽家は演奏することがアウトプットなので
意識して時間をつくりながらインプットすることも大切です。
演奏技術方法、音楽教育、音楽史、世界史、日本史、楽譜の読み込み
音楽理論、絵画、文化・・・際限なく広がっていく・・・
私は今、様々な曲を聞きながら
どんなプログラムができるかを考えています。
「子どものためのコンサートだったら
あの曲とこの曲を組み合わせて、どんなお話をしようか・・・」
「自分を追い込むようなチャレンジコンサートをするならば
あの曲を勉強してみたいなぁ・・・」
「絵本コンサートの短いバージョンだったら
どんな曲が良いかなぁ・・・」
妄想ですね。
この時間が私には重要だったりします。
楽譜を眺めながら時代背景を調べ
自分の話を膨らませるような共通点を探したり
作曲家の時代と今の時代を比べてみたり
あれこれ妄想を広げていくと
楽譜や本の中に埋もれていて
他の生活業務が中途半端に転がっている状態です。
オーガナイズが必要だなぁ・・・
と思ったときは
自分で自分の状態を俯瞰して
自分のホームポジションに戻る。
ヴァイオリニストとライフオーガナイザーを
行ったり来たりしながら進む毎日は
自分を実験台にして
自分に問いかけながら
自分自身を収めていく。
引き籠りすぎてもいけないけれど
インプットなしでアウトプットはできない・・・
生きていくということは
なかなか難しいものです。
21「カーボンボウ(弓)について」
2025/01/21こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。
カーボンボウ(弓)をご存じですか?
弓は本来、フェルナンブコという木を使用したものですが、
近頃はカーボン弓を購入し、使い分けて弾く方もいらっしゃいます。
過酷な演奏状況、通常とは違った弾き方を要求される場合などに便利です。
野外での演奏や大きな生音を必要としないミュージカルや演劇の演奏など。
私も時々、セカンドボウと決めている弓(安価な弓)で演奏をするときもあります。
弓の大掛かりな修理が必要な時は便利ですね。
あとは、カーボンボウは状態が安定しているので
自分の状態を確認するには利用価値がある、ということも言われているそうです。
とはいえ、初心者さんは木の弓をまずは使いましょう。
木の持っているしなやかさ、繊細さ、気候によって変化する弓の状況を感じて
楽器と弓が自分と一体になっていることを感じ取る訓練も必要だと思います。
20「カセットテープの思い出」
2025/01/20
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。
私が幼い頃、発表会の記録はカセットが主流でした。
父が録音担当で、発表会の度に新品のカセットテープを購入して準備していました。
当時、私のヴァイオリンの先生と姉のピアノの先生が合同で発表会をしていたため
プログラムを見ながら、父がとても緊張していたことを思い出しました。
聞き返すのはもっぱら父のみ。
単純に演奏を楽しむだけなので、コメントはありません。
私も姉も、1回聞き返して自分の演奏について不満を漏らして終了…
次の新しい曲に興味が移ってしまって
まともに聞き返すことはほとんどありませんでした。
家族で駐在生活をしていたドイツから帰国した小学校5年生の冬。
古巣の厳しいヴァイオリンの先生にの下に、再び通うこととなり
帰国後2か月で曲を仕上げなくてはならず…
先生の叱咤激励に四苦八苦しながら迎えた発表会で
無事に弾き終えた後「ほぉ~、よくやった~」という父の安堵のため息が
しっかり録音に残っていたことが一番の懐かしい思い出です。
父は私たちの演奏を聴くのをいつも楽しみにしていて
録音したテープをいつまでも、ずっと聞き返していました。
私としては、間違えた個所を思い出したり、ドキドキしたことを思い出したりするので
繰り返し聞かれるのはとても苦手でしたが、父はどこを吹く風。嬉しそうに聴いていました。
カセットデッキもほとんど普及されなくなった後も、時々取り出して聞いていたらしく
たまに「この間、懐かしい曲を聞いたんだよ」と言われて「え…いつの?!」と絶句することもしばしば。
でも、カセットテープの劣化とともに、その回数は減っていたようです。
父の晩年、ふと「このテープをCDに焼きなおしたいなぁ」とつぶやいたことがあり
「それはなかなか難儀だわ。でも、いつかできるといいね」と何気なく答えましたが
忙しさに紛れてその願いは叶わず。
終の棲家となった家の二階に、大量のカセットテープが入ったケースが鎮座して
何度か聞こうと努力した形跡がありました。
その景色に涙しながらも
大量のテープを取っておく場所もなく、
家とともに私の幼いころの演奏は彼方へと消えました。
残しておいた方が良かったかしら?
私自身は、写真も録音も録画も執着がないので
無くなってしまってもがっかりするようなことはありません。
ただ、父がもう少し
私たち姉妹の演奏の成長を簡単に聴くことができたら幸せだったかなぁ、とも思います。
冬空を見上げながら
小学校5年生の発表会が1月末だったことを思い出していました。
19「私の苦手な時期・冬の土用」
2025/01/19
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。
今年は1月17日から冬の土用入り、土用明けは2月2日。
私はこの時期が本当に苦手です。
6月生まれなので、特にこの時期が苦手なのかもしれません。
ドイツに留学していたころから11月と1月は体調がイマイチでした。
身体が硬くて動かなかったり
意味もなく落ち込んだり
失敗が多くなったり…
ヨーロッパの冬はすべてが灰色で
本当に気持ちが落ち込みます。
ヨーロッパ人は日照時間の短さで体調を崩す人がたくさんいます。
太陽のありがたさを感じることを、私はドイツで知りました。
日本に帰国してからは
家族とともに
新しい年を迎えて急発進するような
世の中の風潮にワクワクしたり
心地よい疾走感を感じたものです。
50歳を過ぎたころから
そういった雰囲気に追いつけないことに気がつき
どうしたんだろう
どうしよう、と悩み続け
この2年くらいは無理して頑張ったものですが
今年はあきらめて「引き籠る」ことにしました。
予定を減らし
自宅作業を多くして
居心地よい空間と時間をつくることに専念して・・・
今のところ快適です。
でも油断禁物。
ふとした拍子にガタンと落ち込むこともあるわけです。
ふいに涙が出て止まらなくなったり
倦怠感に襲われて何もできなくなったり…
それを見越して、会いたい人に会う予定を少しだけちりばめています。
そんな「自分の苦手な時期」を把握していると
その時にしかできないことが見つかります。
私の場合は「基本に戻る」
私はヴァイオリンで元にもどるように調整しています。
毎日の忙しさに追われて見失っている「基本」
- スケール(音階)練習でみえてくる音程
- 弓の長さを改めて感じるロングトーン練習
- 右手(弓を持つ方の手)の感覚練習
- ゆっくりと弾くことによる左手の感覚練習
- 無理のない演奏姿勢
どれもゆっくりとした時間の中で
自分と会話しながら進めていきます。
鏡を見て弾いたり
目をつぶって音を聞いてみたり
毎日のルーティンに短時間ずつ取り入れています。
2週間強の冬の土用期間。
今年はなんとかやっていけそうかしら・・・
18「私の冬・洋服事情」
2025/01/18
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。
今日はちょっと気の抜けたお話を。
ヴァイオリンを弾いていると
着れない洋服があったりします。
私は以下のようなものが着れません・・・
- バルキーニット
- 首元の分厚いタートルネック
- 首元にビジューのついたもの
- 襟の硬いシャツ
- 左肩にボタンや飾りのついたもの
- 袖に垂れ下がる飾りのあるもの
- タンクトップや
- ジッパー付きのカーディガンなど…
基本的に首元はシンプルで
腕がまわしやすく
楽器に装飾などが当たらないことが条件です。
私はリサイタルやコンサートが近づいて
練習時間が長くなってくると
おしゃれをする気が失せて
ほとんど毎日同じような洋服を着ていることが多くなります。
(首元に飾りのないシンプルなカットソーとデニム)
今のように寒い冬の時期。
少しだけ練習時間の緩い季節になるので(私の場合)
この時とばかりに
分厚いセーターを着こんで
「寒いわ~、あったかいわ~❤このセーター!」と
おしゃれを楽しんでいます。
冬の時期に私に会う場合
分厚いセーターを着てニコニコしていたら
練習していないな…と思っていただいて良いかと思います。
ちなみに今日は
首元スースーするセーターを着ていました。
17「身体を大切に」
2025/01/17
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。
急に寒くなって身体の動きが鈍いです。
運動神経もそこそこあって
柔軟性もあるので
自分の身体に関しては敏感な方だと思います。
50歳を過ぎてから
特に気をつけるようにしている季節が冬。
身体が硬くなってケガをしないように気をつけています。
階段の昇降、滑りやすい床、ちょっとした段差。
雨の降っている日のマンホールはキケン、ですよ。
楽器を持っているときは、細心の注意が必要。
朝起きた時にゆる~くヨガで身体の芯を起こして
かる~いストレッチを取り入れています。
全行程15分くらいです。
50歳になって、楽器ケースを交換しました。
それまで使っていたケースは重たくて片方の方に掛けるタイプ。
今はケースも少し軽くなって、背負えるタイプになりました。
コロナ禍で、海外のサイトで注文して手に入れました。
ドイツからだったのですが、ずっとフランクフルト空港税関で
出国待ちの状態だったのが、ドイツを出国したと連絡が入ったときには
自宅の前に車が止まって配達完了…という摩訶不思議なことがありました。
多分、今後はこのケースから変えることはないでしょう。
子どもの頃は、ひょうたんケース(楽器の形をしたケース・かわいいです)
音楽高校へ入って青い角ケース(カッコつけたかった!)
その後は何回かケースをかえましたが、いつも角ケースでした。
それぞれのケースに思い出があります。
今どきは、ファッショナブルで軽いケースが多くて目移りしてしまう。
ただ、楽器がちゃんと入るか(たまにサイズが合わなくて入らない場合もあります)
弓がちゃんと入るか(楽器に当たってしまう、長さがケースに合わないなどの例があります)
ちゃんと確かめることが必要です。
ヴァイオリニストは体力が必要!
演奏するにも、練習場所や演奏場所に行くにも
自分で出かけていかなくてはなりません。
共演者に迷惑をかけないことが第一。
自分の身体の状況を冷静にみて
「気分は大丈夫?体調は大丈夫?」と
常に気に掛けることが大切です。
50歳を過ぎたら…
出かけるときは、時間に余裕をもつようにしています。
それだけでも気持ちに余裕ができて
何か起こっても対処する時間ができます。
大人になってからヴァイオリンを始めたい方。
いつでもご相談ください!
楽器ケースの選び方も大切ですよ。
16「どんな曲を聴いているの?」
2025/01/16
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。
いつも聞いている曲はクラシックですか?
そうでないと耳が育たないのでは?
そんなことないですよ!
私の幼少期はアニメ番組のテーマ曲を大声で歌い
「ザ★ベストテン」を楽しみに1週間を過ごし
大人になってからはポップスもジャズも楽しんで
クラシックは、いつも勉強のためにレコード(CD)買っていました。
だから、ヴァイオリンの曲は誰が演奏していても気にならず。
勉強のためなので、音さえわかればいいと思っていました💦
(ちなみにカラオケは苦手ですが誘われたら「津軽海峡冬景色」しか歌いません‼)
「宇宙戦艦ヤマト」の主題歌を歌っていた佐々木功さんや
「いい日旅立ち」「秋桜」などを歌っていた
山口百恵さんは音程がとても良かったです。
子ども心に聴いていて心地よかった。
演歌歌手の方は、特にきちんと歌われるので
聴いていて安心感がありました。
私の両親は、音楽を聴くことについて
特に制約をしなかったので
私も彼らも好きなようにレコードをかけていました。
テレビも好きなように見せてくれたし
母は
気になったアニメの主題歌のレコードを
店頭で歌って買ってきてくれたこともありました…
そのため、音楽高校に入学したころは
往年の有名な演奏家のことを全然知らなくて恥ずかしい思いばかり…
新しく耳にする曲がたくさんあって、途方に暮れました。
同級生のクラシックにかける思いの強さや情熱に
本当に肩身の狭い思いをしていました。
それでも、私にとっては息抜きに聞く映画音楽や
その後の留学時代に聞いていたポップスなどは
心の支えと同時に様々な可能性を広げてくれました。
- リズムの取り方
- 間の取り方
- 息継ぎのしかた
年齢を重ねて
今ではジャズも(頑張って)弾くし
クラシック曲の中にエッセンスとして
ポップスなどの要素を見つけることができるようになりました。
耳が慣れているので
「この曲、ジャズのあの曲みたいだなぁ」と
全然違うことを考えて楽しんだりしています。
今でも幼いころに好きだった曲は歌えますし
楽しい思い出がよみがえってきます。
好きなように
先入観なく
色々な音楽を聴く
子どもには必要な
柔軟な耳を育てる要素になりますよ。
15「自分のペースをはかる・コントロールする・オーガナイズする」
2025/01/15
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。
私は他の人よりペースが遅い方だと思います。
ええっっっ!と驚く方が多いと思うのですが
かなり努力しないと乗り遅れます。
いや、乗り遅れているけれど
そう見えなかったり
つじつま合わせで何とかなってしまったり
勉強して身についていないのに
次々といろんなことに気を取られて
結局無かったことにしてしまったり…
残念な行動をしていることが多いです。
そういったことを改めるべく
今年はブログをコツコツと書いていこうと決めています。
ブログを書くということの習慣化です。
乗り遅れているのは承知しているけれど
どうやったら自分で自分をコントロールできるのか
自分自身をオーガナイズすることができるのか
メンタルの面から整えたいと思っています。
まず私が自分に課していることは
「振り返って見直す」ことです。
前だけをみていたい私の苦手なことです。
でも、振り返りが大切なことはわかっているのです!
シミュレーションをするにも
勉強するにしても、振り返りや復習はとても重要です!
でも、私の場合
あまり慣れていないので
今は1日を振り返ることから始めています。
何を食べて、どんな作業をして、誰としゃべって、何を考えたのか…
カンタンなメモ程度でも書き出すことによって、
思考のクセや変化
パターンが少しずつ見えてきています。
(ほんの少しずつですけれど)
そこからまた次のフェーズへと、
ストレッチゾーンを大きくしていけば良いよね・・・と
自分と相談しながら進めています。
常に自分と相談すること。
とても大切なことだと思っています。
皆さんは自分のことをわかっていますか?
自分と相談して物事を決めていますか?
14「災害時にヴァイオリンはどうする?」
2025/01/14
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。
昨日の夜、日向灘(宮崎県沖)で震度5弱の地震が発生しました。
夜9時過ぎということで、のんびりしている時間
もしくは成人の日のお祝いをしていた方が多いのではないかと思いました。
被害が気になりますが、ずっとニュースを追っていると
私自身の心が疲弊するので距離を取っています。
災害はいつやってくるかわからない。
備えをしましょう…
よく言われることです。
しかし、果たしてどこまで考えれば良いのか途方に暮れます。
私の場合、いつも考えることは
「ヴァイオリンどうする?」
飛行機で何かあったらヴァイオリンはそのまま機内においていく(持っていけないよね)
電車内だったらそのまま背負って退避(なんとしても一緒にいく)
自宅で地震にあったら身を守ったあとで確認(家が崩れてしまったらどうしよう)
楽器を持たずに外出して何かあったら(家がそのままのことを祈るしかないけれど、救出できるか心配)
それ以外は全く考えていないです…
様々な災害を少しだけ想定しながら
「どうする?」というシミュレーションを
頭の中で考えるだけでも良いと思います。
私自身は
大まかな事柄から
少し細かいシチュエーションを考えなくて、と思っています。
先日、横浜防災センターを見学した際に
「自宅の中で安全な場所を見つけておいてください。
どこの柱の陰が良いか、どこの机の下なら安全か、何も倒れてこない場所はどこか。
寝ているときは無防備なので、対策を考えてください」
帰宅してから自宅を見回して、
「案外安全なところって少ないかも💦」と思い直しながら
自分の身を守ることを考えつつ
ヴァイオリンとのことも真剣に考えなければ、と思いました。
新年で浮かれた気分が
キュッと張り詰めた1日。
皆さんは日ごろから災害時に
どんな行動をとればいいか?ということを
考えていますか?
13「成人の日に思いをよせて」
2025/01/13
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。
今日は「成人の日」ですね。
昭和の私は未だにこの祝日がわからなくなって
「1月15日の方がよかったなぁ・・・」って思います。
今年は次女が20歳になったので
盛大にお祝いをしたいところですが
スイス在住のため本人不在での祝宴です。
(音楽史の試験日らしく、昨日は最後の追い込みで
必死の形相をしていました…がんばれ)
次女のことを少しお話ししましょう。
生まれた時から4歳年上の(シスコン)姉に可愛がられ
生後1週間の時に姉の風邪をもらって新生児なのにハナタレ娘…
(新生児は風邪をひかないという説は私の中で消え去った)
姉の行事には常に参加。姉の病院通いにももれなく付き添い。
姉のヴァイオリンレッスンに通うついでに自らヴァイオリンを弾く。(弾かされる?)
幼稚園年中で「私はスイミングスクールに通いたい!」と意思表示して
その後は競泳選手として週6のスクール通い(家から車で40分・小3から電車通い)
ほぼ毎週末の試合と遠征、合宿を経験してメキメキと頭角を現す。
小学4年からJOC大会に連続出場。
小6の夏で「ヴァイオリンに集中する」と宣言して競泳選手引退。
中学の生徒会長をしながらヴァイオリンの遅れを必死に取り戻し
音楽高校受験・合格。
コロナ禍にもめげず、新しい可能性を探り渡欧を繰り返し
海外での音楽修行を選んで高校卒業と同時にスイスに移住。
海外生活の辛酸をなめつつ、
通学時間急行列車1時間の距離をこなしつつ
ただいま大学2回生の秋学期試験期間中。
彼女の強みは競泳選手時代に培った体力。
そして、練習メニューを自分で作って実行したという経験。
周りや自分を冷静に見る姿勢は
競泳のレース配分を戦略的に捉える力と同じなのかも、と思います。
(彼女は200m個人メドレーが得意でした)
20歳になって
自身の責任が重くなります。
親の意見は、今までと違って少し遠いものになるでしょう。
でも、私は信じていたいです。
彼女の今までの経験と知恵、これからの学びによって
どのようにも可能性が開けていくということを。
成人の日に
たくさんの若者がどんな気持ちでこれからを過ごしていくのか。
その思いは、この日本という国を支えていく力になるのだと
期待したいと思っています。
おめでとう!
12「80歳の自分を想像する」
2025/01/12
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。
今日はブログアップが遅くなってしまいました…
今年の初めから地道に書き続けていて
連続記録の更新を止めてしまうのが惜しいので
今日は徒然に書き綴っていきます。
このブログは音楽のことに特化して書こうと決めて
色々なことを思い出したり
記録を調べたり
言葉を選んだりして
楽しみながら書こうと思っています。
私はヴァイオリンとともに50年以上💦
一緒に過ごしています。
そう考えると長い…
その中でも
今までちゃんと弾き続けてこられたこと
応援してくれた人たちに
心からの感謝の気持ちを届けたいです。
ピアノを弾きたいよ~といった私の言葉に耳を傾けてくれた両親。
ピアノではなくヴァイオリンを勧めてくれた先生。
練習曲をイヤイヤながらピアノで弾き続けてくれた姉。
私のつたないヴァイオリン演奏をじっと聞いてくれた悪友たち。
音楽高校・大学で苦楽を共にした友人。
留学時代に長電話に付き添ってくれた友。
オーケストラで一緒にオペラを奏でた仲間たち。
仕事でごいっしょした音楽家たち。
いつも身近で助けてくれた家族。
私とヴァイオリンのことを一番大切に思っていた夫。
私が弾き続けていけるのはあとどれくらいだろうか。
80歳を過ぎても指導している私の師匠は
レッスンで生徒に弾いて見せることは激減しました。
楽器を持って移動するのも、少々難儀のように見えます。
私が80歳になったら、どうしているんだろうか?
その姿を思い浮かべられるようになったら
もっと面白い記事が書けそうです。
「想像できないことは実現しない」
連休の中日、自分の老いた姿を想像するのは
成人の日のせいもあるのでしょうか?
11「練習時間はどのくらい?」
2025/01/11
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。
悩ましい練習時間問題。
「いつも何時間練習しているんですか?」
「どのくらい練習すれば良いのですか?」
この答えに私は即答できませんし
軽々しく答えるものでもないと思っています。
初心者さんとプロは一緒ではないし
音大を目指している方と
趣味でヴァイオリンを弾きたい人と
練習時間は全く違います。
その人に合った練習方法と
目的に合った練習時間。
ヴァイオリンの先生は
その生徒さんをよく見る必要があります。
初心者の子どもだったら
①ヴァイオリンの他にどんな習い事をしているのか
②ヴァイオリンを自分で選んだのか?それとも親がやらせているのか?
③ヴァイオリンへの熱意はどのくらい?
④練習には親が付き添えるの?
⑤どんな曲を弾きたいのか?
⑥学校から帰って来てからどのように過ごしている?
そんなことを始めにヒアリングします。
せっかく始めるヴァイオリンのレッスン。
方向違いのことをしてすぐに辞めてしまわないように。
お話を聞きながら、家で練習できる状態を提案し
それに対しての私からの協力をお伝えします。
動画を撮って模範演奏を贈ったり
メッセージのやり取りを提案したり。
はっきり言えば
レッスンだけでは上手にならないです。
お家での練習はとても重要なのです。
私も母と二人で四苦八苦しました。
母のメモを頼りに、あーでもない、こーでもない。
とにかくレッスンで言われたことは、
次のレッスンではクリアしなければならない。
できなくて何度泣いたことか。
家でも泣いて、レッスンでも泣いて。
小さな楽器はいつでも涙と鼻水だらけでした…
初めのうちは、本当に辛かったです。
先生から言われたことを
ちゃんと覚えておくことが
私には必須だということを叩き込まれた時期でもあります。
おかげで私は、レッスンで言われたことは
楽譜にちょっとメモを残しておけば
録音や録画をする必要もないし
ちゃんと思い出すことができました。
(多少、偏った記憶だったりすることもあり
自分本位な解釈だったりすることもありましたが…
当時はレッスン録音するなんて贅沢はできなかったですからね)
レッスンを受けているのは、誰?
どんなに小さな子どもでも
先生の前で弾いているのは、本人です。
気がついて!
10「私の習い事はじめ」
2025/01/10
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。
今日は少し番外編のようなお話を。
みなさんは習い事を始めるきっかけというのは何でしたか?
「テレビ番組を見て」
「近所のお姉さん(お兄さん)の影響」
「親の勧め」
「気がつかないうちに」等々
私自身は、姉の弾いていたピアノが楽しそうだったので
自分も弾きたいといったけれど、
何だか知らないうちにヴァイオリンを持たされていた…
言い出したのは4歳頃でしたから
それまで習い事の経験はありません。
ただひたすら外で遊んでいました。
外遊びに疲れて帰ってくると
姉がピアノを練習していて
こっそりピアノの下に潜り込んで
寝そべって聞いていました。
ピアノの音が降ってきて
自分を包む感覚が心地よく
低音部を奏でると
心臓部分が揺れる感じが
ワクワクしました。
上手だとか下手だとか
何にもわからなかったけれど
毎日同じ曲を聞くのは嫌じゃなかったです。
「お姉ちゃんの邪魔をしないでこっちにいらっしゃい」と
母に言われても、寝たふりをして動きませんでした。
(姉はイヤだったかもしれないけれど💦)
父が頑張って手に入れたマイホーム。
エレクトーンからアップライトピアノに代わり
そのうちピアノの先生からの斡旋で手に入れた
ヤマハのグランドピアノ。
どういった経緯でそのピアノが我が家に来たのか
わからなかったけれど
その時の父の得意そうな顔は覚えています。
高度経済成長期。
朝から晩まで働いていた父の顔を見れるのは
週末だけだったあの頃。
私たち姉妹と父をつなぐ絆が習い事だったのは確かなことです。
懐かしい思い出です。
今は両親ともに亡くなり
姉は視覚障碍者となってピアノが弾けなくなりました。
でも、あの頃の光景は
鮮やかに私の心に残っていて
キラキラと輝く大切な宝物です。
9「メトロノームは友達?」
2025/01/09
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。
メトロノームって知っていますか?
音楽家であれば、一つ二つ持っている方も多いと思います。
そして、賛否両論分かれるところ…
【メトロノーム】
音楽の速度を測る機器。
オランダの発明家ディートリヒ・ニコラウス・ヴィンケルが考案
ドイツの発明家ヨハン・ネポムク・メンツェルが特許を取得(1816年)
メンツェルの友人ベートーヴェンも利用したとか。
「カチコチいってるだけで耳障り」
「機械のように弾くだけ」
「人間味の無い演奏になる」
ご意見もっとも…
「テンポが安定する」
「反復練習で無理なく弾けるようになる」
「テンポ感がわかるようになる」
良い面もちゃんとあります…
私自身はメトロノームを真剣に使うようになったのは
留学中かもしれません。
難関の弾けそうにない個所を
ゆっくりのテンポから始めて
一コマずつテンポを上げていく。
指示された速度よりほんの少し早いくらいで終了。
毎日遅いテンポからはじめて
数日で弾けるようになります。
そうなれば安心。
メトロノームに頼らなくても大丈夫。
初心者さんにはぜひ、振り子式のメトロノームをお勧めします。
振り子の速度を目視することによって
速さの感覚を追いかけることができ
身体がその動きを感じることができるからです。
振り子の動きに合わせて
言葉を発してみたり
手をたたいてみたり
飛んだり跳ねたり
遊びの要素を存分に活かしてみてはいかがでしょうか。
ただし、時間を決めて
5分程度にしましょう!
メトロノームの音は案外大きいので
耳から離れなくなってしまうから!
8「楽器を構えるのも練習」
2025/01/08
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。
1日練習を休むと自分にわかり
2日休むと先生にわかる
3日休むと聴衆にわかる
有名なよく知られている例えですね。
1日休むと戻すのに3日かかる、とも言われます。
本当かどうか?
それは個人差になりますが
要するに
「一度練習を休んじゃうと、ペースを戻すのが大変だよ~」
という意味です。
毎日何時間も練習するのは本当に大変です。
正直、練習を休みたいときもあります。
でも、プロは知っています。
休んだ後の戻りが遅くて自分にイライラしてしまうことを・・・
初心者さんは
本当に少しの時間で良いので
楽器に毎日触ってください。
小さいお子さんは、毎日10分でいいから
楽器ケースを開けましょう。
大人の生徒さんは、10分で良いので
楽器を構えてみましょう。
楽器を毎日構えていると
自分の身体にヴァイオリンのフォルムがフィットしてきます。
ヴァイオリンを弾く姿勢は
決して自然な形ではないので
どれだけラクに
負荷がかからないように弾くか、
ということも
大切なことだと思います。
最初に我慢して
悪い姿勢で弾き続けていくと
いつか身体が悲鳴を上げて
弾けなくなってしまいますよ。
「痛いところはないかな?」と
自分に聞いてみてください。
もし、痛いところや違和感があれば
先生に相談してくださいね。
身体の大きさ
骨格の違い
手の長さ
手の大きさ…
それぞれの最適な姿勢があります。
せっかく始めたヴァイオリン。
「なんだか痛いところが多いからやめる~」なんて言わずに
先生と相談しながら
辛抱強くしばらく続けてみましょう。
さて私も、今日の練習を始めますよ。
7「動画を使っての練習とレッスン」
2025/01/07
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。
練習のお話。
大人の生徒さんは練習時間の捻出に苦労します。
ヴァイオリンっていうのは、
楽器と一緒にどれだけの時間を過ごすかによって
上達は違ってきます。
ヴァイオリンを弾くことは憧れだけど
練習していても、これで良いのか自信がない…
そんな時は、自分の練習風景を動画で撮って
先生に送信する!
私の生徒さんには動画講評形式のレッスンも承っています。
コロナ禍で激増したオンライン形式のレッスン。
ただ、相互でWi-Fi環境が整っていないと
レッスンするのは正直難しかったです
zoom機能は、元々電話会議用に設定されているため
音楽を再生するにはかなり無理があったようです。
私はそんな時、動画を送ってもらって
それに対しての講評を
テキストメッセージで返信するスタイルにしていました。
(1曲丸ごとじゃなくて、部分的に3分くらいが良いです)
更に、自分の演奏を生徒さんに送って
自主練習の役に立つようにしていました。
(二重奏の曲を先生と一緒に弾けますよ~)
☆弾けない日があっても先生の動画をみるだけでOK!
☆先生の音源と一緒に指を動かしてみる!
☆先生の音源を流しっぱなしにして聴くだけ!
大人の生徒さんだけではなく
子どものためのレッスンにも有効です。
今の時代は、工夫をすればたくさんの選択肢が選べて
勉強をする意思があれば
何でもできますね。
先生自身もどん欲に学びを深めていかなければ!と
思っています。
6「練習は弾くことだけじゃない」
2025/01/06
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。
練習に関する話題は尽きませんね。
今週は練習についていろいろとお話してみましょう。
「練習は嫌い」
「子どもが練習をしてくれない」
「どうやったら練習が好きになるのか」
「効率の良い練習方法を教えてほしい」等々
プロの私でも教えてほしい内容です。
効率よく弾けるようになるのであれば・・・
苦も無くスラスラ楽譜が読めるのあれば・・・
間違いなく音程がきちんと合うのであれば・・・
凡人の私には練習しかない、とあきらめて
毎日、楽器ケースをそろそろと開けながら
ゆっくりとヴァイオリンを取りだし
弓を適切に張り
松脂をつけて
楽器を構えます。
…と、ここまでの動作、あなたは無意識にできますか?
そう、ヴァイオリンを始めたばかりの子ども(大人)は
ここまでの道のりも一苦労なのですよ。
私がピアノに憧れた一つの理由として
「ピアノのふたを開けたらすぐに弾ける」という
単純動作が好きだったことが挙げられます。
しかし、ヴァイオリンは弾けるようになるまでの状態が遠い。
乱暴に扱うと簡単に壊れてしまうので神経を使う。
私の生徒さんには
「まず楽器に慣れることを習慣にしてください」
と言って、
毎日楽器ケースを開けて
ヴァイオリンを弾ける状態になることを練習課題にしています。
そして、どんなに小さい子どもでも、
【自分で】その準備をするように伝えています。
決して親が先回りして用意しないように。
もちろん、親が横について見守ることは必須ですが
時間がかかるから、と親が手を出すことはご法度です。
それが約束できない小さなお子様のレッスンはお断りしています。
【自分で自分の楽器を準備する】
それも練習なんです!
レッスンに来るときも、楽器は自分で持ってくるように伝えます。
お母さんが大事そうに楽器ケースと楽譜カバンを抱えて
子どもが手ぶらで歩くなんて・・・NGですよ。
もちろん、人込みや電車内はお母さんが代わりに持っていても良いです。
でも、先生のお宅の前で子どもに持たせましょう。
私の母は、家を出てバスに乗るまで私に楽器を持たせ
道中は母が楽器ケースを抱えて電車に乗り
先生の玄関先で私が再び持つ、ということをさせていました。
家を出てからバス停まで、なぜ自分で持たせたか?
近所の人に「親がやらせている感」とみられないため、だったらしいです💦
私自身は「ヴァイオリンを習っている特別感」だけを頼りに
意気揚々と楽器ケースを持っていました(単なるミーハー)
今は良いですね。
肩に背負えるタイプのものが増えています。
私の時代は取っ手を持つタイプか、片方の肩に掛けるタイプのものしか無かったので
楽器ケースは本当に邪魔でした…
50代の今、軽くてスタイリッシュな楽器ケースに巡り合って
移動が楽になりました💛
5「練習の苦行」
2025/01/05
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。
外遊び大好きな私の課題は、なんといってもヴァイオリンの練習でした。
とにかくずっと遊んでいたい…
隙あらば外に出て自転車に乗って走っていたい…
私の母は「4時半になったら練習しなさいよ~」とだけ
毎日私に叫んでいました。
なぜか?
そう、姉が5時半過ぎからピアノの練習をするからです。
練習室なんてものは存在しないので、ピアノもヴァイオリンも練習はリビング。
姉は真面目で時間通りに事が進むことを望みます。
中学校から帰ってくるのが5時過ぎ。
その後、夕食までの時間をピアノ練習に充てたい。
そんな時に、ノソノソ妹が聞くに堪えないヴァイオリンを弾いていてほしくない。
妹の方が早く帰って来ているのだからサッサと練習を済ませておいてほしい。
母は姉から文句を言われていたのでしょうね。
母から焦って「早くしなさい~。お姉ちゃんが帰ってきちゃうわよ~」と呼ばれて
私はしぶしぶ、しょうがないので帰宅してヴァイオリンのケースを開けるだけで
あくびが出てきてしまう。
楽器を準備するのも一苦労(楽器をそろそろと出して、弓の毛を点検して松脂をつける)
調弦(4本の弦をチューニングする)も難儀。
楽器を構えるのもさらに大変で、ああでもない、こうでもない。
弦に弓を置いて音程を合わせるのなんて!
なんでヴァイオリンってのは難しい楽器なんだ!!
母も横について、ヴァイオリンの先生がおっしゃっていたことを書き留めたメモを片手に
色々と工夫してみても、肝心の私がしっかり弾かなければ何の音も出ない…
私もなんとか努力してみるも、良いのか悪いのかサッパリわからない…
今思えば、よく続けていたなぁと思います。
最終的には、姉にピアノで音を弾いてもらって
その音を頼りに音程を合わせていきました。
レッスンに行っても、音程が違う!と怒られてばかり。
同じ時期に始めたお友達はスラスラと滑らかに奏でているけれど
私はいつまでたっても「音程が違う」ばかり言われていました。
このころの私は有無を言わずに
「4時半になったらヴァイオリンの練習をする」
という習慣を刷り込んでいた時期だったと思います。
それ以上は母も期待していなかったのかもしれません。
それも大切なことだと思います。
弾けるようになるには、練習するという習慣が必要です。
その時間をどこに設定するのか?
私には選択肢がなかったので「4時半」でしたが
生徒さんの中には「お風呂から上がってパジャマに着替えたら」という子もいました。
親心としては「朝7時」なんていう朝練に惹かれますが
私自身が娘たちに試してみたところ
学校へ送り出す前にヘトヘトになってしまうので
自分の身がもたないので止めました。
相対的には、学校から帰宅してすぐに練習、という生徒さんが
多かったように思います。
私自身は、自分(親)が先に管理しようとして失敗することが多々ありました。
その子自身の個性や最適な時間が必ずあります。
その時間を色々と試してみるには、やはり時間が必要です。
長くヴァイオリンを弾いていきたいのであれば
そんなプロセスを飛ばすことなく
お子さんの個性をたくさん発見しながら進めていくことも
大切なことの一つなのではと思います。
私は今もなお
4時半前後にソワソワとしてしまう自分がいます。
4「本物の感覚」
2025/01/04
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。
幼いころの私はヴァイオリンより外遊びが大好き。
近所に住む同い年の友達と
一日中庭を駆け回り、
公園へ出かけて鬼ごっこ、
田んぼで走り回って(冬限定:夏は蛇が田んぼを泳いでいるので怖くて近寄らない)
冬枯れの野原でひっつきむしをくっつけて帰宅して
怒られる…の繰り返し。
その当時流行っていたリカちゃん人形やこえだちゃんの木のおうちを
友だちも私も持っていなかったため
他の友達と遊びの仲間に入ることができず
ひたすら外で遊んでいました。
その時の私に「よくやった!」と褒めてあげたいことがあります。
それは自然の息吹を感じ取る感覚の鋭さを養ったからです。
なんとなく空の色が違うからお天気が変わりそう。
なんだか雨のにおいがするよ。
春が近づいてるね。
なんだか日暮れが早くなって帰る時間が早くなったかも。
冬の田んぼはポクポクしてるよ。
霜柱はザクザクしてずっと踏みしめていたい!
あの頃は四季の移り変わりが
今よりもっとはっきりだったからかもしれません。
でも、感覚が自然のリズムをちゃんとキャッチしていたように思います。
それらは家に帰って母が
「台風が近づいてきているから気圧が変化していて頭が痛いわ」
「今日は啓蟄だから、私の嫌いな長い生き物が土から出てくるのよね」
「秋の日はつるべ落としっていうのよ。スッと陽が落ちて寂しいわね」
「もう、冬至ねぇ。ストーブの上に干し芋のおやつがあるわよ~」
と会話したことが今でも耳に残っています。
あなた自身
もしくはあなたの子どもさんは
そんな感覚を持っていますか?
音楽はそんなことを全部ひっくるめて表現するのです。
どんな色で、どんな音で、どんな味覚で、どんな香りで、どんな肌触り?
自分の喜び・彼女の怒り・あの人の悲しみ・小さな小さな楽しみ・・・
どんな曲を弾くにも
それらが必要になってくるのです。
子ども時代にどれだけたくさんの経験をして
どれだけ心に刺激があったか。
それらが本物であればあるほど
音楽の原石はゆっくりと美しく磨かれていきます。
ちなみに私の娘たちも感覚は鋭く
音感とは別に
経験値は私を上回って
様々な感情や感覚を持っていると思います。
それを素直に表現するか
少し熟成させて表現するか、というのは
その人の個性になるのではないかと思っています。
3「お正月の思い出」
2025/01/03
こんにちは、ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。
姉がピアノ。
私がヴァイオリン。
小さい頃はブツブツ言いながら姉が私のピアノ伴奏を弾いてくれました。
自分の練習で手一杯なのに、妹の曲まで弾かなきゃならなくて
大変だったと思います。
まだ私が幼稚園や小学校低学年のころ、
年始になると、父が嬉しそうに私たちの演奏を聴いてくれました。
「弾き初め」は毎年1月2日。
午後のまったりとした時間に、おもむろに楽器をとりだして
練習途中の曲を披露すると「ほっほっほ~」と笑いながら拍手してくれて
母がその横で「今年も頑張らなきゃね~」と笑っていました。
姉のピアノは真面目で神経質ながら、音楽の流れが自然で
私の波動にぴったりなところが大好きでした。
「いいなぁ、あの曲を弾いてみたいな」といつも羨ましく思ったものです。
父は事あるごとに、私たちの演奏を来客に聴かせました。
海外駐在中は、日本からの出張者が自宅に訪れることが良くありました。
母がキッチンで髪を振り乱してごちそうを作っている間に
「ちょっと何か弾いてみなさい」と客間に呼ばれ
まだまだ仕上がっていない曲を弾かされました。
私はヨロヨロと練習途中の曲を途中まで弾き切り
「ここまでです」とチョコンとお辞儀をして終了。
姉は「え、まだ仕上がっていない曲を弾くのは嫌だなぁ」と
軽い文句を言いながらも父に逆らえず弾く。
それでも、お客様は喜んでくださり、父は鼻高々でした。
演奏に対してのコメントをすることはなく
お客様にも過度に自慢をすることもなく
全くの自己満足の領域だったように思えます。
でも、それこそが私がずっと続けていられた源泉だったのかもしれません。
人前で弾く、という音楽家には当たり前のことを
ごく自然に経験させてもらったように思います。
練習中の曲をそのまま弾く、というところが
何とも父らしく。
あらかじめ弾けるような曲を準備しておくといった
小細工をしなかったのは素晴らしいなぁ、と思います。
聴いてくださったお客様にはお耳汚しだったかもしれませんが
細工されたものより興味深かったのではないかと思います。
たとえそれが、父の自己満足だったとしても
私たち姉妹には、未だに語れる良き思い出です。
2 「見方を変える」
2025/01/02
こんにちはヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。
昨日は簡単すぎる自己紹介で
ヴァイオリンをはじめたきっかけをお話しました。
実は・・・
私の娘2人も、ヴァイオリニストです。
(正確に言えば修行中でしょうか)
この事実を「すごい!」と感じるか
「くどい💦」と感じるか「ありえない~」と感じるか…
娘たちは私の存在をそこはかとなく意識はしていますが
邪魔だとは思っておらず
自分らしい音楽を創っています。
私たち3人の音楽は、アプローチが全く違うので
良い関係性を作り上げたのではと思っています。
私自身も、娘たちがヴァイオリンを弾くにあたって
気をつけたことがありましたし
彼女たちも努力した部分がありました。
ということで
私自身は「ヴァイオリンを習わせてもらった」という視点からも
「ヴァイオリンを習わせた」という視点からも
お伝えできることがあるということです。
「視点を変える」というのは大切なことで
私自身も自分の経験を基盤にしながらも
娘たちのサポートは、視点を変えて見つめるようにしました。
*言語化の練習中なので頑張って書きます~
1 新しい年によせて
2025/01/01
こんにちは、ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。
今年からこちらのブログを始めてみようと思っています。
音楽に関してのことを中心に、音楽生活、音楽教育、音楽とともに暮らすことについてお話していければと思います。
私は4歳からヴァイオリンを始めました。
自分からヴァイオリンを選んだわけではなく
6歳年上の姉がピアノを弾いているのが羨ましくて「自分も!」と思っていたのですが
「あなたはヴァイオリンね」というピアノの先生の一言で私の音楽人生が始まりました。
練習よりも外遊びが大好きで、近所の友達と公園や田んぼを駆け回り
母から「早く練習しなさい~!」と怒られてばかり。
レッスンに行ってもうまく弾けないうえに
「あら、日本語がわかるのかしら?」とあきれられる…
音楽だけの生活を送っていたわけでもなく
テニスをしたり、体育の授業もバスケやバレーが得意で
真剣に体育大学に進学しようかと考えたこともあり…
それでも弾くことが好きで続けていたら
50年以上もヴァイオリンとともにいる…
ものすごく短く言えばそんな感じでしょうか?
(端折りすぎです💦)
「弾くことが好きで続けていたら・・・」の中に含まれる様々なことを
これからお伝えしていきたいと思います。
何かあなたの音楽人生や音楽家への疑問が
私のブログを読むことによって
ホッとしたり、納得したり、考えを深めるきっかけになればと思います。
どうぞよろしくお願いします!
関連エントリー
-
 23「リサイタルの準備はじめています」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。今年のリサイタルのプログラムを思案中です。この
23「リサイタルの準備はじめています」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。今年のリサイタルのプログラムを思案中です。この
-
 24「一日を彩る音たちとともに」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。寒い毎日。外出を極力控えて家にこもっています。
24「一日を彩る音たちとともに」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。寒い毎日。外出を極力控えて家にこもっています。
-
 25「春の兆しを感じる1日」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。年下のお友だちとの女子会。クリエイティブなお仕
25「春の兆しを感じる1日」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。年下のお友だちとの女子会。クリエイティブなお仕
-
 26「冬の光を実験する」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。試験的に色々な写真を撮っています。被写体は色々
26「冬の光を実験する」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。試験的に色々な写真を撮っています。被写体は色々
-
 27「お花のサブスクが運ぶ思い出」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。先日、毎月届くお花の定期便にフリージアが入って
27「お花のサブスクが運ぶ思い出」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。先日、毎月届くお花の定期便にフリージアが入って