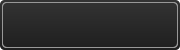- ホーム
- ブログ
ブログ

30「週末の音楽との距離感」
2026/01/30
『1月も終わりに近づいてきました』
寒い毎日は頭も体も縮こまって冬眠気味の私には、
焦らずにのんびり生きていこう!という気持ちになります。
全力疾走した日々を思い返すと、怠惰に見える今の自分。
立ち止まっているように思える今の時間。
でも、生きているだけで毎日は螺旋状に変化しているものです。
大丈夫、自分と相談しながら過ごす日々にしていこうよ!
と意識を変化させています。
週末になると、音楽との距離が少し変わります。
平日は
「ちゃんと弾こう」
「ここを整えよう」と
自分の練習にもダメ出しが多くて
「弾けない~」と言いながら
あれこれ考えて
頭が先に行くのですが
週末は音そのものを楽しむ時間が増える気がします。
完璧じゃなくてもいい音。
途中で止まってもいいフレーズ。
いつか弾いてみたいなぁ、と思っている曲。
時間を気にせずに、
短時間でもよいから楽器のケースを開けて一音だけでも弾いてみる。
窓からの光や空の色、風の音と一緒に音を出すと、
ああ、本当に音楽って生活の一部なんだな、と思います。
金曜日は週末モード。
今週もお疲れさま。
みなさまの週末に、心地よい音が流れますように。
29「イヤホンが苦手な理由」
2026/01/29
電車の中でイヤホンをしている人を、ちょっとうらやましく思うことがあります。
音楽を聴いていたり、勉強をしていたり、本の内容を聴いていたりするのでしょうか。
時間を上手に使っているように見えて、格好良かったりします。
そして、人がたくさんいる場所でも、ふと自分のパーソナルスペースを作れるのは良いなぁと思います。
私はどちらかといえばイヤホンが苦手で、特に音楽はスピーカーで聞きたいと思っています。
音楽は、その音に集中することも大切ですが、その周りにある音も一緒に聞いてこそだと思っています。
たとえば、コンサートに行って、会場にあふれる雰囲気や話し声、客席や天井を見上げて感じる空気もその音楽の一部です。
スピーカーから聞こえる音楽も、その日のお天気や気分によって聞こえ方が違います。
それらをしっかり味わうためには、私は断然スピーカーが一番だと思っています。
ただ、私は自分が『耳の閉所恐怖症』なのかもと思っています…
(閉所恐怖症の方がイヤホンをするとパニックになるという事例がありますが、それとはちょっと違う)
イヤホンはその音だけしか聞こえないので、他の音が遮断されてしまいます。
視覚的には普段の生活なのに、耳からの情報は音だけ。
私にとっては聞こえる音と視界のギャップに混乱している状態。
そんなに深刻ではありませんが、イヤホンを遠ざけるひとつの理由です。
そうはいっても、人知れず自分だけ聞けるという便利なイヤホン。
私も好んでイヤホンを選ぶときもあります。
私の利用法は、ネガティブマインドに陥ったとき。
ちょっとアップテンポの曲を選んで、ひたすら掃除をする・・・
トイレ掃除、排水口掃除、鍋みがき、模様替え。家の中でできることが条件。
(庭の掃除などは、近所の人にあいさつされることが多いので、イヤホンは不向き…)
1時間もすれば、ホッと一息ついて何かしらの方向性が見えていることが多いです。
どちらにせよ、常に音楽は私の身近にあるわけなので
切っても切れないご縁、なんですよね。
イヤホンの発達があったために、オンラインが身近になり、遠くの人と繋がれるようになりました。
イヤホンのおかげで、手軽に一人の時間が得られるようになって、人との距離感が多様になりました。
でも、ちょっとまって。
それだけで安心しないで。
時にはスピーカーの存在を思い出してほしいです。
忘れかけていた、「リアルな音=生きている音すべて」を思い出す必要もありますから!
【イヤホンの遍歴】
1979年:ウォークマンが登場して音楽が持ち運びできるようになる
2000年代:「カナル型」が主流
2017年頃から:ワイヤレスの台頭
近年:ノイズキャンセリング機能の充実28「健やかに生きる」
2026/01/28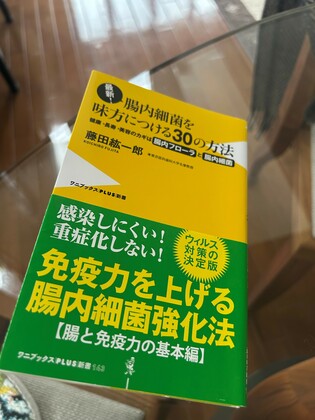
27「お花のサブスクが運ぶ思い出」
2026/01/27
「私は母のために花を絶やしたくなくて
いつもなにか、生花を飾っていました。自分のためでもありました。」26「冬の光を実験する」
2026/01/26
-
 22「似た者同士?」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。デジタル機器に疎い私は何か不具合があると焦りま
22「似た者同士?」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。デジタル機器に疎い私は何か不具合があると焦りま
-
 23「リサイタルの準備はじめています」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。今年のリサイタルのプログラムを思案中です。この
23「リサイタルの準備はじめています」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。今年のリサイタルのプログラムを思案中です。この
-
 24「一日を彩る音たちとともに」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。寒い毎日。外出を極力控えて家にこもっています。
24「一日を彩る音たちとともに」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。寒い毎日。外出を極力控えて家にこもっています。
-
 25「春の兆しを感じる1日」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。年下のお友だちとの女子会。クリエイティブなお仕
25「春の兆しを感じる1日」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。年下のお友だちとの女子会。クリエイティブなお仕
-
 26「冬の光を実験する」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。試験的に色々な写真を撮っています。被写体は色々
26「冬の光を実験する」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。試験的に色々な写真を撮っています。被写体は色々