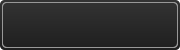45「音楽家と言葉」
2025/02/14
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。
音楽家は音で曲を表現するので
どちらかというと言葉をおざなりにしがちです。
「表現するのが難しいけれど・・・」
「言葉にできないから、こんな感じ・・・」
「なんとなく、こんな風に・・・」
私もピアニストに細かいニュアンスを伝えるときに
曖昧な言葉で逃げてしまう時があります。
また「とにかく弾いてみましょう・・・」と
時間を気にして次のステップへ行ってしまう時もあります。
でも、
近頃は、なるべく少しでも何かが伝わるように
言葉をかえてみたり
例を挙げてみたり
反対方向から伝えてみたり、と
意識的に言葉を使うようにしています。
急がば回れ
じっくり伝えた方が
相手が「あぁ、なるほど」と
充分に理解することができたり
納得することができたり
腑に落ちるということができているように感じます。
伝えるときに
自分の思っているぴったりの言葉を
選び取ることの大切さ。
それは日本語だからできることかもしれません。
日本語は素晴らしい言語だと思います。
何かを説明するにも
多様な言葉が存在します。
英語やドイツ語は
ひとつの事柄に対しての単語の数は
そう多くありません。
どちらかといえば
直接的で
簡潔で
ひとつの言葉が
どのシチュエーションでも
使いまわすことができます。
(私はそれで助けられています💦)
英語もドイツ語も
ストレートに伝えたいことを言ったり
わからないことを質問することができるからです。
・・ラクです・・
でも、日本語にある様々な
ニュアンス
言い回し
陰に隠れた真意(を、ぼかすテクニック)
ひっかけ問題的な言葉のあや・・・
などを使い分けることの
楽しさや難しさは
母国語だからできることです。
そのひとさじの言葉の塩梅(あんばいって日本語らしいなぁ)を
意識的に使いこなすことができるのなら
音楽を奏でることも
もっともっと、ずっと奥深いものになっていくのではないかと思います。
子どもの生徒さんには
「読み聞かせをしてもらったり、自分で本を読んでみましょう」と
声掛けをします。
大人の生徒さんにも
「時間がないことは重々承知していますが、本を読むクセをつけましょう」と
お勧めしています。
私自身も、様々なジャンルの本を
楽しく(時間がなくて苦しく・・・)読んでいます。
週末に、本屋さんに行って本を選んでみませんか?
関連エントリー
-
 23「リサイタルの準備はじめています」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。今年のリサイタルのプログラムを思案中です。この
23「リサイタルの準備はじめています」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。今年のリサイタルのプログラムを思案中です。この
-
 24「一日を彩る音たちとともに」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。寒い毎日。外出を極力控えて家にこもっています。
24「一日を彩る音たちとともに」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。寒い毎日。外出を極力控えて家にこもっています。
-
 25「春の兆しを感じる1日」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。年下のお友だちとの女子会。クリエイティブなお仕
25「春の兆しを感じる1日」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。年下のお友だちとの女子会。クリエイティブなお仕
-
 26「冬の光を実験する」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。試験的に色々な写真を撮っています。被写体は色々
26「冬の光を実験する」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。試験的に色々な写真を撮っています。被写体は色々
-
 27「お花のサブスクが運ぶ思い出」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。先日、毎月届くお花の定期便にフリージアが入って
27「お花のサブスクが運ぶ思い出」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。先日、毎月届くお花の定期便にフリージアが入って