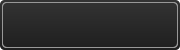89「海外音楽修行②・次女」
2025/03/30
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。
今日は次女の話をしましょう。
次女は高校生活を日本で終えて、大学生からスイスへと勉強の場所を移しました。
音楽高校時代はコロナ禍全盛期。
音楽家として若い時に研鑽を積まなければならないオーケストラの授業や室内楽、
演奏会などが軒並み中止や延期になる厳しい時間でした。
長女と部屋も寝室も一緒だったため、姉妹での話は頻繁だったようで
大学を海外で過ごそうという目標はわりと早く訪れたように思います。
コロナ禍でも、自分の技術不足を補うためにコンクールへ参加してみたり、
オンライン講習会に参加してみたり、
規制が緩んだタイミングで渡欧する経験を重ねていました。
こちらもすべて自力。
正直に言えば、私自身が演奏活動や地域活動に忙しく、
更に父の介護も始まっていたので十分なサポートができませんでした。
フライトチケットやホテルの相談はもっぱら夫の役目。
夕食後の時間は夫と娘たちがそれぞれのパソコンを持ち寄って、
ヨーロッパの状況やレート計算、ホテルや移動手段の相談でした。
高校生だった次女にはハードルが高いことが多かったのですが、
高3の夏には3週間の一人旅。
講習会を渡り歩き、移動も一人でスーツケースと楽器を背負って汗だく。
「なんだか黒いTシャツが白く塩が吹いてるのよ」
と笑いながら写真を送ってくる姿を頼もしく感じたりして。
秋になってようやく巡り合えた教授に決めてから、フランス語の勉強が本格化しました。
大学課程は座学があるので講義はすべてフランス語。
我が家には仏語のわかる人がいないので、次女は孤軍奮闘。
話題に哲学や政治経済の話が一般的なフランス人の先生との会話に
「クジラの乱獲について考えを述べるなんて、日本語でもしたことないんだけど・・・」
と言いながらレッスンに通っていました。
高校を卒業して一旦、単位履修生としてそのまま音大に通い始めた4月に父親が突然亡くなるという気が遠くなるような途方もない経験。
スイスの音大入学試験直前のことでした。
ほぼ同時に私の父も余命1ヶ月を宣言されていた時期でした。
すべてが崩壊しそうなとき、とにかく入学試験へ行くと決めたのは次女自身でした。
父親の葬儀の5日後でした。
「私はじさまの葬式には間に合わない。だから全部をお願いする」
と言いおいてやせ細った次女を見送るのは苦しかったです。
本来であれば入学試験を受けながら、街の様子を見学して住む場所の目星をつけて、秋学期の始まる直前に父親と一緒に契約するという予定を組んでいたのですが、予定を変更して教授の知り合いのお宅の一室を間借りするということになりました。
スイスで部屋を借りるというのはなかなか難しいです。
そもそも18歳の娘が部屋を借りることが難しい。
スイス人の保証人が必要と言われることが多いです。
しかし、スイスは小国であり、生粋のスイス人を見つけることが難しい!
間借りしていたお宅から移るときも、良い部屋に恵まれず、
保証人問題、親の収入問題(父親の死去と私の収入がないこと)などで学生寮も断られる始末で途方に暮れました。
結局、ひょんなことから知り合った音楽家のご夫婦のB&B用のスペースを借りることになり、私自身は心底ホッとしました。
スイスに移住してから、食べ物やストレスから蕁麻疹や体調不良が続いて心配でしたが、
私も自分の状況が厳しかったためfacetimeでのサポートしかできず、寝不足の日が続きました。
住まいが安心安全であれば、学校生活もほんの少し軽減されます。
本当は誰にも煩わされることのない一人暮らしが良かった次女の心中は複雑だったようですが、次の機会に期待してもらいましょう。
学校までの距離も列車で1時間強ということですから、近いわけでないので移動のストレスもあるようですが、何とか若さで乗り切ってもらいたいものです。
1年目は、一人で頑張らなきゃ、と背伸びをしてかなり危ない橋を渡ったこともあったようですが、覚悟をしたうえでの軌道修正はいつでも可能だと伝えています。
「○○せねば、○○すべき」という気持ちだけでは、気持ちが辛くなるだけになってしまう危険があります。
次女に関しては、辛い気持ちになったら日本に短期間の一時帰国を選択肢に入れても良いし、あまり切り詰めた生活にならないように伝えています。
とはいえ、自分で学校に奨学金の申請をして授与してもらう手続きをし、しっかり私を支えてくれている逞しさもあります。
自分の家庭環境について、二人ともそれを言い訳にしない強さを持っています。
なぜ、自分が海外で勉強しているのか?
なぜ、私はここにいるのか?
覚悟と決断を重ねたからこそ、
二人とも小さなステップを重ねながら
着実に歩いている姿を見せてくれているのだと思います。
-
 44「りうまーミートアップ@東京に参加しました」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。りうまーミートアップ@東京に参加しました。昨日
44「りうまーミートアップ@東京に参加しました」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。りうまーミートアップ@東京に参加しました。昨日
-
 45「ホームページを改良していきます」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。私のホームページはずっと放置状態でした。自分の
45「ホームページを改良していきます」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。私のホームページはずっと放置状態でした。自分の
-
 46「二十四節気とともに季節を歩いていく」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。少しずつ春の息吹を感じる毎日です。木々の新芽が
46「二十四節気とともに季節を歩いていく」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。少しずつ春の息吹を感じる毎日です。木々の新芽が
-
 47「積読・2月の進捗」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。積読その後の状況・・・着実に消化しています。(
47「積読・2月の進捗」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。積読その後の状況・・・着実に消化しています。(
-
 48「無伴奏曲を弾くとき」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。今年のリサイタルの曲目を絶賛思案中。頭の中がい
48「無伴奏曲を弾くとき」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。今年のリサイタルの曲目を絶賛思案中。頭の中がい