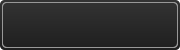166「続・本を読む」
2025/06/15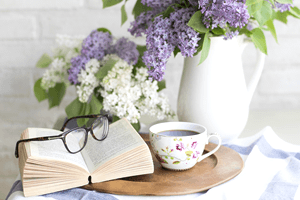
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。
本の感想文は得意ではないのですが
備忘録も含めてメモ程度に書こうと思います。
本を読むことは好きですが
時間がないと思い込んで読むのをあきらめていたりすることがあります。
今週は庭整備のために職人さんが出入りしているため
スケジュールに余裕があるので読書三昧の日々にしようと思っていました。
「わたしの渡世日記 上下」高峰秀子(文春文庫)
「巴里ひとりある記」を読了後にすぐ読んだため、合点の行くことが多く納得感もあった。
とにかく読み応えのあるエッセイだった。
毎週1回分、1年にわたるエッセイ。
それも1回分が原稿用紙10枚以上(4000字)なのだからものすごいことだと思う。
それを物書きではない女優が書き上げるのだから「えらいこっちゃ」である。
戦前から戦後までの間、高峰秀子という子役から女優へと進む道にある、様々な人間関係と出来事と世界情勢と、混とんとした彼女の心が浮き彫りになる。
子役としての仕事のため学校へも行けず、毎日毎日撮影所の往復。
『子供にとっての一番の喜びは「学問」以前に「子供同士が友だちを作りあう」ことであり、「生まれて初めての小学校における「集団生活」の経験だと、それをついに持つことの出来なかった私は、自信を持っていうことができる。』
『せめて子供のときくらいは、自然な子供の世界で、子供らしく遊ばせ、子供同士の会話を持たせてやってほしいと私は願う。』
『子供には、感受性はあっても、大人の鈍感さはない』
(以上文中より)
彼女の切実な思いは、今の時代にも心に残る。
私の子育てを振り返るきっかけにもなった言葉たち。
学校へ行きたいという願いも、人気絶頂の彼女にはその選択が現れては消え、結局学校へ通うことができなかった。
だが、彼女には常に【本物の「師」】が常に周りにいた。
監督や俳優、職人から財界人、文豪や芸術家などありとあらゆる人。人間関係ほどすべての勉強に勝るものはないかもしれない。
本物を目の当たりにして、それを無我夢中で対峙することによって磨かれた感性。
だが、それらも素地がないとやはり偽物にすりかわってしまうことだろう。
そして彼女自身も、基礎的な勉強はやはり大切なことだと彼女自身も悟っていたはずだ。
「無知な人間ほど無謀である。」(文中より)
そう思って教えを乞う時には必死の形相だっただろう。
演じるために頭をフル稼働させて想像力を働かせる。
戦前戦後の激動期を、映画を撮るというプロフェッショナルなことに従事して
世情に翻弄されながらも女優として生きていた。
養母との確執を、切ろうと思っても切れない縁は
たとえ自分が稼いだ賃金であっても
生活を支えたのは養母だとわかっていたから。
その、彼女の心意気が文字に表れていて心が痛かった。
「ほかに喜んでくれる人がいなかったから、自分で喜ぶよりしようがなかった。」(文中より)
結局、それができる人が利口である。
「可哀そうに、君は人間として、言葉は悪いが片輪なんだね」と結婚した松山善三に言われてホッとする彼女。
それまでの道のりをあきらめずに不貞腐れずに歩いていた彼女の姿に清々しさを感じた。
関連エントリー
-
 24「一日を彩る音たちとともに」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。寒い毎日。外出を極力控えて家にこもっています。
24「一日を彩る音たちとともに」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。寒い毎日。外出を極力控えて家にこもっています。
-
 25「春の兆しを感じる1日」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。年下のお友だちとの女子会。クリエイティブなお仕
25「春の兆しを感じる1日」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。年下のお友だちとの女子会。クリエイティブなお仕
-
 26「冬の光を実験する」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。試験的に色々な写真を撮っています。被写体は色々
26「冬の光を実験する」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。試験的に色々な写真を撮っています。被写体は色々
-
 27「お花のサブスクが運ぶ思い出」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。先日、毎月届くお花の定期便にフリージアが入って
27「お花のサブスクが運ぶ思い出」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。先日、毎月届くお花の定期便にフリージアが入って
-
 28「健やかに生きる」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。50代後半になってくると健康に関心が高くなって
28「健やかに生きる」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。50代後半になってくると健康に関心が高くなって