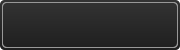84「留学の思い出④」
2025/03/25
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。
私が留学して2年目を過ぎたころから
オーケストラ入団を目指して職探しをする学生に目が向くようになりました。
ドイツのオーケストラは当時、なかなかポジションが空かなくて
オーディションを受けるのもかなり大変でした。
申し込みをしても書類審査で落とされることが多いのです。
留学するために奨学金を取り損ねた私は
父に迷惑をかけないためにも
少しでも働きたいと思っていました。
そんな時に、各オーケストラには「Praktikum(プラクティム)」という
インターンシップ制度があることを知りました。
学生のためのポジションですが、半分の勤務体制で
オーケストラで学びながらしっかりとお給料も支給されるというもの。
住んでいる都市のオーケストラが
そのポジション(第1ヴァイオリン)のオーディションが行を行うとのことで
なんとしても合格したくて頑張りました。
オーディションは下記のような課題曲がありました。
- モーツァルトの協奏曲から第1楽章とカデンツァ
- ロマン派の協奏曲の第1楽章
- 指定されたオーケストラスタディ(交響曲やオペラの中にある指定された場所)を演奏する
指示された協奏曲は弾きなれたものでしたが
オーケストラスタディだけは、経験が無かったので指導教授に
レッスンしてもらって勉強しました。
- 指定されたテンポで弾くこと
- テンポの中で音楽的に演奏すること
- 他のパートを頭の中で鳴らしながら弾くこと
幸い、日本の高校大学でのオーケストラ経験が大いに役立って
弾くことに苦労することはなかったように思います。
最初の仕事はシュトラウス作曲の「ばらの騎士」の中で
舞台袖で演奏するバンダでした。
第3幕途中での演奏なので、同僚たちが演奏中に控室に行って準備し
他のバンダ仲間と共に袖に行き、指揮者に合わせて演奏し
終わるとそそくさと帰る・・・というもの。
始めは何を着ていけば良いのかもわからず
指定された時間で本当に良いのか
ドキドキしながらオペラ座に行ったものです。
その後はシンフォニーコンサートとオペラの仕事。
シンフォニーコンサートは5日間の練習期間と
3回の定期演奏会。(その当時は木曜夜公演・金曜夜公演・日曜昼公演)
オペラの仕事のインターン生は、
そのシーズンでリニューアルした演目のオペラを
オーケストラリハーサルから、歌手とのリハーサル、舞台リハーサル
通し稽古・本通し稽古・初日以降もずっと弾いていました。
その作品は忘れもしない「マハゴニー市の興亡」(クルト・ヴァイル)
そのうち、様々なオペラ作品を弾かせてもらうことになり
特にワーグナーの作品はほぼ一通り弾いたかもしれません。
(ニーベルングの指輪4部作・ローエングリン・さまよえるオランダ人
タンホイザー・トリスタンとイゾルデ・パルジファルなど)
他のオーケストラでこんなにたくさんのワーグナー作品を演奏する場所はなかったので
とても貴重な経験でした。
(ワーグナー作品を歌える歌手が限られることと、指揮者がいない。
指輪4部作は1週間で全作演奏するので、演奏者も慣れていないと大変です)
オペラ座にはバレエ団もあったので
バレエの曲もたくさん弾きました。
(バレエは難しい曲が多く、譜読みに苦労しました)
団員向けに安価なチケットが準備される制度もあるので
友だちに見に来るように誘ったりしました。
オーケストラピットで演奏していると
舞台で何が行われているか知らず
「全然違う解釈で面白かったわ!」と言われても
「へええ・・・」と言うしかなかったりして…
クリスマスも新年も日本へ帰ることが少なかったので
休暇を取りたい同僚の代わりに嬉々として演奏していました。
大みそかの日はたいていミュージカル仕立ての「マイ・フェア・レディ」の公演があり
楽しくて幸せな気分で舞台を終えて帰宅すると夜の11時を過ぎているので
そのまま起きて日本の両親に新年のあいさつの電話をすることもありました。
インターン生の面倒をみるのはたいてい古参の団員。
私の担当は引退を2年後に控えたおじさんでした。
古き良きレコード時代の話と逸話をたくさんしてくれました。
音楽の中にかくれているモチーフの音を得意げに鳴らしたり
オペラのセリフを演者と同じように口パクで演じたり
私がいちいち驚く表情をするとさらに饒舌に語ってくれましたが
同僚のみんなは「また始まったよ」とばかりにニヤニヤしていました。
彼は仕事を終えて退勤するのが早く
「じゃあまたね!」と握手をして終演5分後には
ハンチング帽をかぶって颯爽と控室を出ていっていました。
まぁ、他の団員も退勤は早くて
聴衆よりも早く市電に乗り込むことが多かったです。
とにかく早く家に帰る!
彼らの姿勢は徹底していて、とても参考になりました。
私が今でも撤収が早いのは
この頃の名残かもしれません。
そして
決められた時間は最善を尽くして演奏に集中するが
仕事ではないことには徹底的に排除する。
労働組合の主張もしっかりとしていて
その毅然とした態度に驚いたことも多々ありました。
私にとって忘れがたく
楽しくて生き生きとした時間でした。
関連エントリー
-
 44「りうまーミートアップ@東京に参加しました」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。りうまーミートアップ@東京に参加しました。昨日
44「りうまーミートアップ@東京に参加しました」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。りうまーミートアップ@東京に参加しました。昨日
-
 45「ホームページを改良していきます」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。私のホームページはずっと放置状態でした。自分の
45「ホームページを改良していきます」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。私のホームページはずっと放置状態でした。自分の
-
 46「二十四節気とともに季節を歩いていく」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。少しずつ春の息吹を感じる毎日です。木々の新芽が
46「二十四節気とともに季節を歩いていく」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。少しずつ春の息吹を感じる毎日です。木々の新芽が
-
 47「積読・2月の進捗」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。積読その後の状況・・・着実に消化しています。(
47「積読・2月の進捗」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。積読その後の状況・・・着実に消化しています。(
-
 48「無伴奏曲を弾くとき」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。今年のリサイタルの曲目を絶賛思案中。頭の中がい
48「無伴奏曲を弾くとき」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。今年のリサイタルの曲目を絶賛思案中。頭の中がい