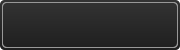- ホーム
- ブログ
ブログ

325「違うフィールドをさがす」
2025/11/21
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。
今月で地域での比較的大きなお役目を退任します。
そのため、今は引継ぎ関係の真っただ中。
書類等々を見直して
次の方がわかりやすいように整えたり
メモを作ったり
自分の活動を振り返ったり。
思ったより、活動が多かったことに驚きつつ
よく時間を捻出していたなぁ、と
自分の行動をほめたたえたり。
気がつくとあっという間に時間が過ぎていて焦ります。
送別会があったり、挨拶をしなくてはならず
そういうことの苦手は私はアタフタしています。
コンサートのMCはストレスに感じないのですが
ちょっとした挨拶が苦手です・・・
それでも、お世話になったことは
きちんとお伝えしたいと思っています。
辞めると決めてから
少し不安になったりしたのですが
次の出会いやチャンスを探しに
自分のフィールドを大きくしていきたいと思っています。
324「心を活性化させる演奏を」
2025/11/20
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。
先日は、ミニコンサートのために
練馬区へ行ってまいりました。
前半が教養講座。後半がピアノとヴァイオリンのコンサート。
地域の方が思いのほかたくさんいらしていて
ビックリしました。
私たち演奏者も講座を聴くことができて
学びがありました。
(ホワイトボードで区切られた空間でしたが
身体を動かしたりしながら聴けるという・・・
ありがたい状況でした。)
その時の様子はフェイスブックに投稿しました。
年齢を重ねて
様々なコンサートに対応できるような
度胸がついてきたように思います。
聴いている方たちと一緒に楽しむ。
真剣に弾く・聴く。
共演者の川元真里さんの支えもあって
最後まで楽しい時間でした。
アンケートも
「とても楽しかった!」
「生演奏が聴けてリフレッシュできた」
「うっとりしてなみだが・・・」
「曲の解説もあってよかった」など
好評でホッとしました。
323「クリスマスコンサートin地域」
2025/11/19
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。

11月も後半。
今年のコンサートも残り少なくなっています。
12月は毎年恒例の「音の旅人ヴァイオリンリサイタル」
この大きな舞台へ臨むために
1年を過ごしていると言っても過言ではないかもしれません。
自分の立ち位置を確かめる大きな舞台。
今年もぜひ、楽しみにしていてください!
そして今年はその4日後に
地域の親子ひろばで絵本コンサートを開催します。
編成がガラリと変わってヴァイオリンデュオ。
クラシック音楽入門編なのですが
内容はかなり本格的です。
私たち演奏者も真剣に奏でます。
(かなり)難曲揃いなので
今からすでに緊張しています・・・(気が早すぎ)
子どもたちにとって
初めてのヴァイオリンの音になるかもしれない、と思うと
ついつい気張ってしまいます。
でも、真剣になりすぎると怖い音楽になってしまいますね。
まずは先入観なく
楽しんでいただきたいと思っているので
リラックスして聴いていただきたいです。

322「MC付きコンサートは仕込みが大事」
2025/11/18
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。
どんなに小さなコンサートでも
どんなに短い曲でも
本番が終わるとホッとします。
近頃はMC付きのコンサートが増えて
内容を考えるのも準備の一つになりました。
まず
目的のコンサートの趣旨や対象者
場所などを考慮してプログラムを考えます。
その後は、MCをどのように配置するのか
どんなに内容にするのか大まかに決めて
細かい部分はその時の雰囲気に合わせます。
なかなかハードルが高いMC付きコンサートですが
お客様とのコミュニケーションを楽しめるので
私自身も準備に念を入れます。
以前は、演奏とMCが中途半端になることが多く
落ち込むことも多かったのですが
場数を踏んで臨機応変にできるようになりました。
ただ、仕込みはきちんとしなくてはならない・・・と
胆に銘じています。
私の場合は行き当たりばったりでは上手くいかないので・・・
曲目解説等は、しっかりと確認が必要なので
今後も間違いがないように勉強を続けていこうと思っています。
そして大切なのは共演者。
私が何を話していても
その場の雰囲気を
ちゃんと理解してくれる共演者の存在は
とても大切で頼もしい存在です。
お客様も、そんなところを見ていただけたら
楽しいかと思います。
「なんだか楽しくて勉強になったかも」
そう思っていただけたら、最高に嬉しいです。
321「苦手をそのままにしない」
2025/11/17
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。
超絶技巧の曲は得意ではありません。
そんなに器用ではないし
手の大きさもそれほどでもないので
身体的に無理のある曲は選びません・・・
でも、名曲として有名な曲の中には
難しい曲がたくさんあります。
一筋縄ではいかない曲。
自分の苦手とする音型の並ぶ曲。
それらは地道な練習が必要です。
今日は一日
音としては単純なのに
どうしても弾けない部分を
執拗に練習しました・・・
何度も何度も
頭と指が連動して弾けるように。
気がつけば夕方。
50代になると
若い頃のようにサッとできることが少なくなります。
指が動かない。
疲れやすい。
それでもあきらめずに
くさらずに
黙々と弾いていきたいものです。
さて、明日は少しでもスムースに指が動くのでしょうか?
たのしみです。
関連エントリー
-
 23「リサイタルの準備はじめています」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。今年のリサイタルのプログラムを思案中です。この
23「リサイタルの準備はじめています」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。今年のリサイタルのプログラムを思案中です。この
-
 24「一日を彩る音たちとともに」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。寒い毎日。外出を極力控えて家にこもっています。
24「一日を彩る音たちとともに」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。寒い毎日。外出を極力控えて家にこもっています。
-
 25「春の兆しを感じる1日」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。年下のお友だちとの女子会。クリエイティブなお仕
25「春の兆しを感じる1日」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。年下のお友だちとの女子会。クリエイティブなお仕
-
 26「冬の光を実験する」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。試験的に色々な写真を撮っています。被写体は色々
26「冬の光を実験する」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。試験的に色々な写真を撮っています。被写体は色々
-
 27「お花のサブスクが運ぶ思い出」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。先日、毎月届くお花の定期便にフリージアが入って
27「お花のサブスクが運ぶ思い出」
こんにちは。ヴァイオリニストの塚本香央里(つかもとかおり)です。先日、毎月届くお花の定期便にフリージアが入って